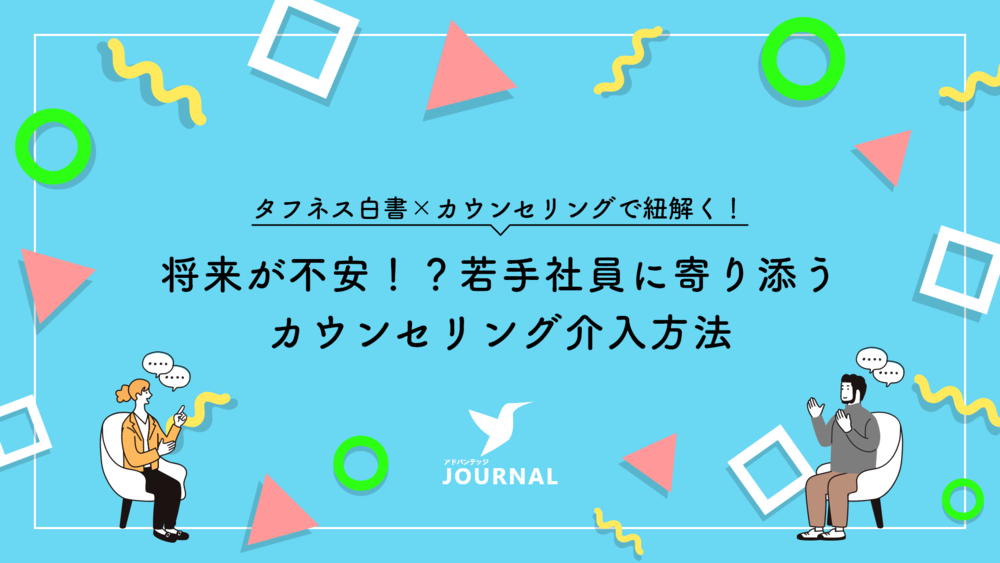「自社の将来を担ってくれるはず」と期待していた若手が退職する、苦労して採用したハイパフォーマーが半年も経たずに辞めてしまう。これは、人事担当者にとっても、企業にとっても大きな痛手であり、適切に対処しなければさらなる人材流出につながりかねません。優秀な人ほど見切りが早いことには理由があり、一定の傾向がみられます。本記事では、優秀な人が離職を選ぶ背景や兆候、企業がすべき対策について解説します。
目次
優秀な人ほど職場への見切りが早い理由とは?

はじめに、優秀な人が早々に職場を去ってしまう理由を、優秀な人の思考や傾向から紐解いていきましょう。
成長できず停滞することを避けたいから
優秀な人は、自分の将来のビジョンやキャリアを具体的に描いています。仕事は、それを実現するステップとして認識しているため、自己成長が感じられず「停滞」を認識した瞬間に、新たな挑戦ができる場所に目を向けるのです。
現状と将来像のギャップを敏感に察知するから
現状と将来のギャップを敏感に察知できることも、次の行動が早い理由です。優秀な人は、常に長期的な視点を持ち、今の仕事が自分の目指すキャリア像と一致しているか、組織の持続的な成長が可能かどうかを見極めています。「収入が十分であってもこれ以上のキャリアは目指せない」「業績が安定していて経営上の問題はなくても、これ以上組織が成長する見込みは薄い」などと判断すると、見切りをつけて去ってしまいます。
時間を無駄にしたくない意識があるから
「このままこの企業にいては自分の価値が下がる」「現状維持は無駄になる」と損失の可能性を認識すると、新たな道に進むために行動を始めます。特に20~30代の従業員は、タイパを重視する人も多く、「早いうちに多くのスキルを身につけたい」「この年代だからこそ挑戦できる」「今ならたとえ失敗しても挽回できる」と考え、シビアに判断を下す傾向にあります。
見切りが早く優秀な人の性格タイプ

見切りが早く優秀な人は、性格面でも共通点があります。ここでは、3つの性格要素をご紹介します。
決断力がある
優秀な人は、決断力があります。現状を冷静にかつ論理的に分析し、目標達成のために必要なことが何かを迅速に判断できます。仕事においても、問題の本質を見極め的確な解決策を講じられるほか、撤退や中止の決断も早いです。衝動的に「辞める」という判断をしているのではなく、「自分にとって最善の選択である」と判断し、行動に移します。
自己効力感が高く、向上心がある
優秀な人は成功体験を重ねていることも多く、どんな環境でも自分の力を発揮できるという自信を持っています。また、向上心が高くスキルアップのための研鑽を怠らない面もあります。今の仕事で自分の力を活かせないと感じると、迷うことなく新たなキャリアを探し始めるのです。常によりよい環境、成長できる環境を求めてアンテナを張っているため、チャンスを逃すことがありません。
柔軟な思考を持ち、適応力が高い
変化を「成長のチャンス」として前向きに受け入れ、新しいことにも積極的に挑戦していける適応力があります。「新しい職場が合わなかったらどうしよう」と環境の変化をリスクとして捉える人も多い一方で、優秀な人は「変わらないことこそリスク」と考えるのです。「うまくいかなかったら次を探せば良い」と柔軟に受け止め、変化を恐れずに行動ができます。
優秀な人が見切りをつけるサイン・前兆

優秀な人が職場に見切りをつけ、転職を検討し始めたり、次の職場が決まったりすると、言動にも変化がみられるようになります。ここでは、優秀な人が退職しそうなサインをご紹介します。
消極的な態度
優秀な人が退職を考え始めると、仕事への取り組み方に変化がみられることがあります。例えば、新しいプロジェクトへのアサインを断る、中長期的な案件を避けるなど、仕事に対して消極的になることもあるでしょう。責任感が強い人ほど、「辞めるつもりなのに無責任に引き受けられない」「引継ぎが手間になる」と考え慎重な姿勢をみせます。改善の提案や前向きな発言が多かった人が意見を出さなくなったり、指摘をしなくなったりしたら注意が必要です。
コミュニケーションの減少
離職の意思が芽生えると、周囲のメンバーとのコミュニケーションが減ります。例えば、できるだけ会話を避ける、ランチや飲み会に参加しなくなるなどの行動です。水面下で転職活動を進めていて、面接の日程調整や連絡をするために1人で過ごす時間を作りたいと考えていたり、転職の意思を悟られたくないとあえて距離をとったりしています。挨拶など、基本的なコミュニケーションが減った場合には、心理的な変化が起きている可能性があります。
勤務時間・休み方の変化
勤怠状況の変化も、退職の兆候としてみられるサインの1つです。残業をしていた人が定時で帰るようになる、有給休暇の取得頻度が増える、休みの申請が直前になっているような場合、面接など転職活動の予定が入ったとも考えられます。
身だしなみの変化
服装や髪型など、身だしなみの明らかな変化も退職のサインです。ラフな服装だった人がきちんとした装いになる、髪型がしっかり整えられているなどの場合、採用面接の予定が入ったとも考えられます。身だしなみの変化のみでの判断は難しいものの、他の要因と併せていくつか思い当たることがあれば、退職の意思が確かなものとなっている可能性が高いです。
優秀な従業員が辞めていく理由について、詳しくは以下の記事でも解説しています。
優秀な人が見切りをつけやすい職場の共通点

優秀な人に見切りをつけられてしまう職場にも、共通の特徴があります。
業務量が多く負担が大きい
効率よく仕事をこなすことを評価され、優秀な人だけに仕事が集中し、結果として業務の負担が重くなるケースがあります。すると、より労働環境や労働条件の良い職場を探して離職してしまいます。またワークライフバランスが崩れると、心身の不調を引き起こすことにもつながりかねません。
適切な評価が得られない
働きぶりや成果が正当に評価されない環境では、優秀な人材のモチベーションは大きく低下します。曖昧な評価基準、上司の恣意的な判断が多く含まれた評価、年功序列を重視する文化では、成長やキャリアアップが阻害されてしまいます。また、昇進に必要な成果や条件が不透明なままでは、キャリア像を描きにくく、不信感を抱くこともあるでしょう。成長意欲の高い優秀な人ほど、「ここではきちんと評価してもらえない」と感じやすいものです。「自分を正当に評価してくれる職場を探そう」と転職を考えるきっかけになります。
心理的安全性が低い
優秀な人に限らず、職場の人間関係の問題は離職理由の上位に挙げられます。改善の提案やアイディアを提案しても否定される、ハラスメントが日常的に存在する職場では、自分の能力を十分に発揮できないうえに、心理的なストレスも大きく、安心して働けません。心理的安全性が低い組織には早々に見切りをつけ、より働きやすい職場へと移っていくのです。
自己成長を実感できない
仕事が単調で学びがない、新しい挑戦ができない環境では、成長を実感できずやりがいを見出せません。「スキルの幅が広がらない」「ここではもう学べることがない」と感じると、キャリアを停滞させる環境に身を置き続けることを避け、新たな職場に移ります。
組織の将来性がない
優秀な人は、自社の経営戦略やビジョンにも目を向けており、将来性がないと感じると去っていってしまいます。変化を拒む組織風土や、保守的で挑戦が認められにくい文化、主体性や熱意の低い従業員の存在は、優秀な人にとって大きなストレス要因となり得ます。他社が柔軟に変化していく中で、自社だけが変わらない状態にあると、「ここにいても成長できない」と感じ、より将来性のある企業への転職を考えるようになるのです。
優秀な人の早めの見切りを防ぐために企業ができる対策
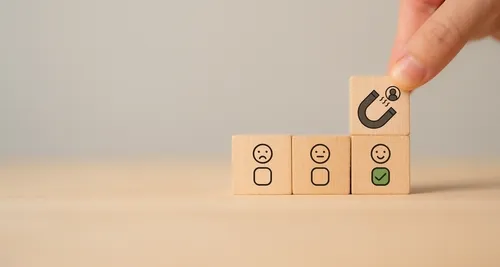
優秀な人の離職を防ぐためには、「働きやすいか」だけでなく「働き続けたいか」という視点でも仕組みや制度を整えていくことが大切です。最後に、企業が取り組むべき離職防止対策についてご紹介します。
業務の負担軽減・裁量権の拡大
優秀な人に業務が集中し、負担を感じている場合は、割り振りやプロセスを見直し、業務量を調整します。同時に、裁量権を拡大し本人の判断で進められる範囲を広げます。また、年齢や入社年次、役職にかかわらず、実力のある人材にはリーダーのポジションを任せるなどして、活躍の場を設けましょう。
ただし、裁量を与えても「最終的な責任は上司が負う」という姿勢の明確さが重要です。安心して挑戦できることで、優秀な人が持つ力をスキルや能力を存分に発揮しやすくなり、やりがいや達成感を高められます。上司は細かい指示を出すのではなく、信頼して任せるスタンスが大切です。
評価制度の見直し
成果や努力が正当に評価される仕組みがなければ、優秀な人は離れていきます。客観的で明確な評価基準を設け、納得度の高い制度に刷新しましょう。360度評価など、多面的なフィードバックを取り入れるのも有効です。併せて、昇進や昇格の要件など、キャリアアップのステップについても明文化し、透明度を高めます。
コミュニケーションの活性化
表向きには問題なく業務をこなしていても、内面ではキャリアや自己成長について不満を抱えていることもあります。上司は定期的な1on1ミーティングなどを通して、業務への向き合い方や目標、課題などをヒアリングしましょう。日常の業務の中でも、仕事ができるからと任せきりにするのではなく、コミュニケーションをとることを心がけ、モチベーションの低下や離職の兆候を早期に察知できるようにします。
挑戦できる機会の提供
さらなる成長を求める従業員のために、挑戦できる機会を提供しましょう。例えば、部門横断のプロジェクトや新規事業へのアサイン、自ら部署異動を希望する社内公募制度(社内FA制度)などがあります。「やらせっぱなし」ではなく、フォローアップなどの機会も用意しながら、着実に成長を実感できる環境作りが大切です。
また、副業や兼業を認め、「自社ではできないこと」を外で経験してもらえば、優秀な人材の成長や満足度の向上も期待できます。外部で得た経験や知見を社内でも活かせれば、企業としてもプラスになるでしょう。
キャリア形成・学びの支援
一人ひとりが望むキャリアの実現をサポートすることも重要です。キャリアパスを可視化し、「この企業で働き続ければ理想のキャリアが築ける」と感じてもらうことが必要です。キャリアデザイン研修や、個々のキャリアプランに合わせた目標設定の支援などを行いましょう。
定期的なサーベイの実施
従業員がどのような姿勢で仕事に取り組んでいるのか、何に不満を抱えているのかを把握するためには、定期的なサーベイの実施が有効です。エンゲージメントやモチベーション、人間関係など、さまざまな角度から質問し、目にはみえづらい組織課題の発見につなげます。
特に、短期間かつ高頻度で行うパルスサーベイは、変化の把握に長けているため、離職の兆候などを早期に捉えることも可能です。サーベイ結果を分析し、課題の把握と組織改善のPDCAを回していきましょう。
優秀な人が働きやすく、働き続けたくなる職場へ

優秀な人ほど、現状を的確に見極め、自分自身の望むキャリアの実現に向けて、よりよい選択を速やかに行います。「見切りをつけられてしまう企業」にならないためには、その能力を正当に評価できる制度と、成長を支援する取り組みが不可欠です。1on1による対話やサーベイを通して、従業員一人ひとりと真摯に向き合い続けていくことが、人材の定着と企業の成長に寄与するでしょう。