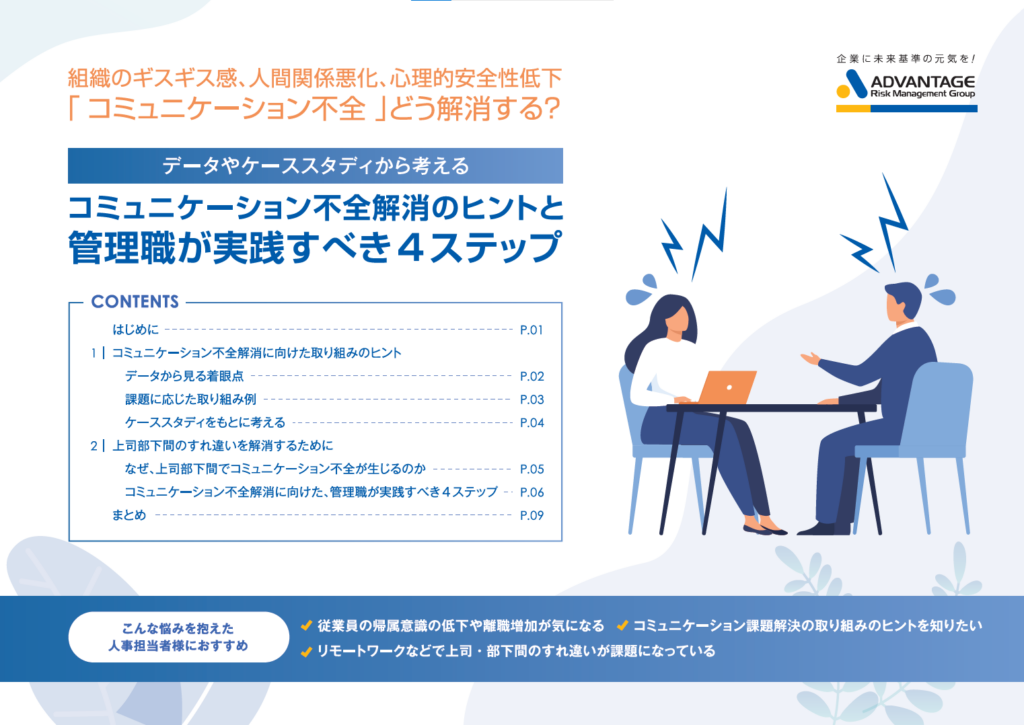少子高齢化による労働者人口の減少は、企業の人材確保をより困難にしています。今後ますます採用活動は苦戦することが考えられるでしょう。
さらに、近年はせっかく採用した社員がさまざまな理由で定着せず、離職してしまう人材流出が課題となっています。
新卒・中途採用に関わらず社員の離職防止としてリテンションマネジメントが注目されています。この記事ではリテンションマネジメントの重要性と具体的な取り組み事例について解説します。
目次
リテンションマネジメントとは
リテンションマネジメントとは「優秀な人材の離職を防ぎ、その能力を発揮できる状態を作る人事施策」のことを指します。
リテンションマネジメントは、社員の離職防止やエンゲージメント向上だけではなく、人材定着による採用・教育コストの抑制効果、社員の活躍による労働生産性の向上、企業イメージや顧客満足度の向上といった、多数のメリットがあります。近年、多くの企業が注目し力を入れています。
厚生労働省の「平成30年若年者雇用実態調査の概況」によると、すでに7割以上の企業が若手社員の定着のために何らかの施策を実施しています。中でも「職場での意思疎通の向上」「本人の能力・適性に合った配置」は、半数以上の企業が取り組んでいます。
リテンションマネジメントの重要性
リテンションマネジメントの重要性が高まっている理由には、求職者に有利な人材市場と、近年の働く価値観の変化の2つがあります。
求職者に有利な人材市場
少子高齢化による労働人口の減少に伴い、有効求人倍率は高い状態で推移しています。コロナ禍で景気が不透明になりながらも、2021年卒の大卒求人倍率は1.53倍、2022年卒は1.50倍と堅調です。
中途採用市場も、2021年上期にはコロナ禍以前の水準を超える市況となり、第2新卒~40代のミドルクラスまで幅広い求人が出ており、求職者有利の人材市場が、以前よりも転職へのハードルを下げています。
社員は会社に不満があれば我慢をせずに、自分がやりたいことのために、あるいは働きやすい環境を目指して転職できる状況です。人事は採用もさることながら、まず優秀な人材の流出を防ぐための施策を考えなければいけないでしょう。
働く価値観の変化
人材流出が止まらないのは、社員の働く価値観が変わっているのも大きな要因です。
今の若い世代は終身雇用が事実上崩壊していることを理解しています。また、キャリア教育を受けてきたため、自分のスキルアップや成長のためによりよい職場を求めることにポジティブな感覚を持っています。大手企業からベンチャーに転職する人も少なくありません。
Z世代に顕著ですが「会社の役に立ちたい」といった企業への忠誠心よりも「社会の役に立ちたい」「自分の能力を高めたい」といった社会貢献意欲、自分の能力向上への意識が強いという特徴もあります。 早期離職を防ぐためには、このような新しい価値観を理解したうえでエンゲージメント向上に有効なリテンションマネジメントをおこなうことがカギとなるでしょう。
リテンションマネジメントの取り組み事例

ここでは、離職防止に有効なリテンションマネジメントの取り組み事例を4つ紹介します。
①社内コミュニケーションの活性化
・1on1ミーティングを取り入れる、いつでも相談できる雰囲気を作る
・入社後半年~1年は同期同士の接点を毎月設定する
・メンター制度、ブラザー・シスター制度を取り入れる
・制度にこだわらず、上司との縦のコミュニケーションだけではなく、同期や部署内の同僚との横のコミュニケーション、他部署の先輩社員との斜めのコミュニケーションを活性化させ風通しをよくする
②「働きやすさ」を整える
・待遇や勤務環境などに関して、同業他社と肩を並べる水準にまで引き上げる
・そのうえで、ジョブローテーションや人材公募制度などを導入し社内でのキャリア形成に魅力を持たせる
③キャリアアップの支援
・1年目の後半、3年目、5年目などの節目で研修やミーティングを実施しキャリア開発を支援する
・直属の上司に研修を実施し、新入社員の特徴を理解した育て方を今一度学んでもらう
④会社の方針や姿勢を打ち出す
・共感を呼ぶような会社の方針や姿勢を、明確に打ち出す(社内にビジョンが浸透することで自身の役割は会社の方向性にどう結びついているのか明確になり仕事への納得度が増す)
・トップが社内外に積極的、継続的に理念やメッセージを発信する
・上司がトップのメッセージをかみ砕き、新入社員でも腹落ちできるように伝える
まとめ
近年の求職者に有利な人材市場、若者の働く価値観の変化によって、リテンションマネジメントの重要性が高まっています。リテンションマネジメントは、社員の定着率向上と優秀な人材の流出防止につながる重要な施策です。
今後、少子高齢化はさらに進んでいきます。優秀な人材を新卒で確保することが難しくなるだけでなく、中途採用市場での人材争奪戦が激しくなっていくので、優秀な人材が流出していくリスクも高まるでしょう。
魅力のある企業づくりは、付け焼刃ではできません。今こそ、リテンションマネジメントに取り組み、ポテンシャルの高い人材の育成に力を注ぎ、社員が働きやすく、働きがいの持てる魅力ある職場環境を整えていくことが重要です。