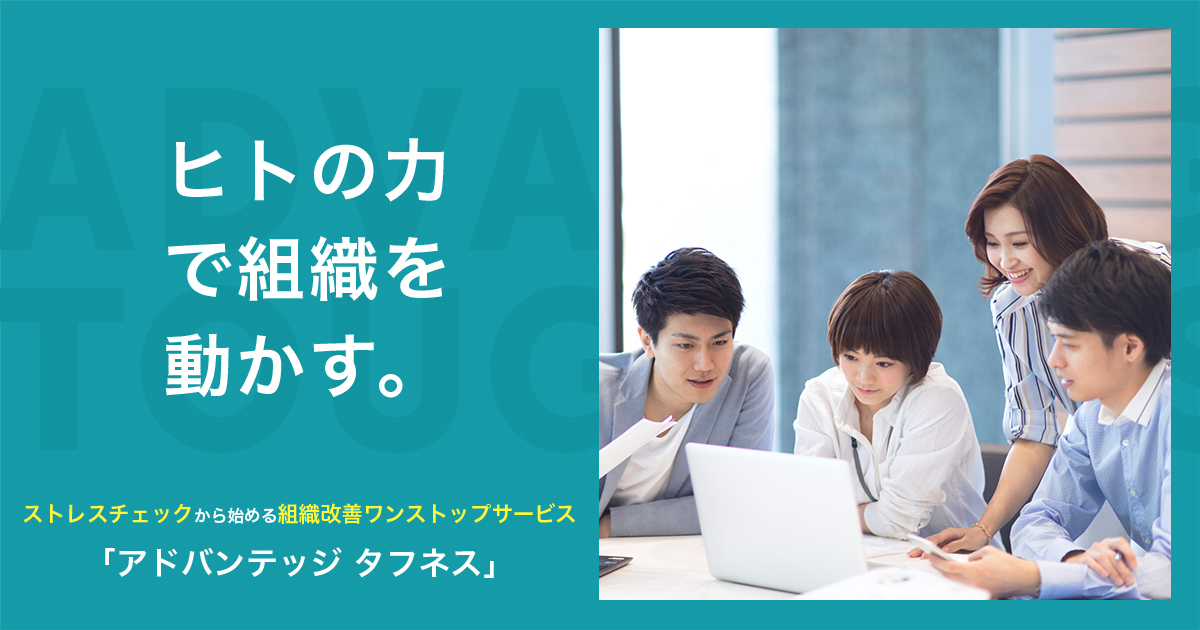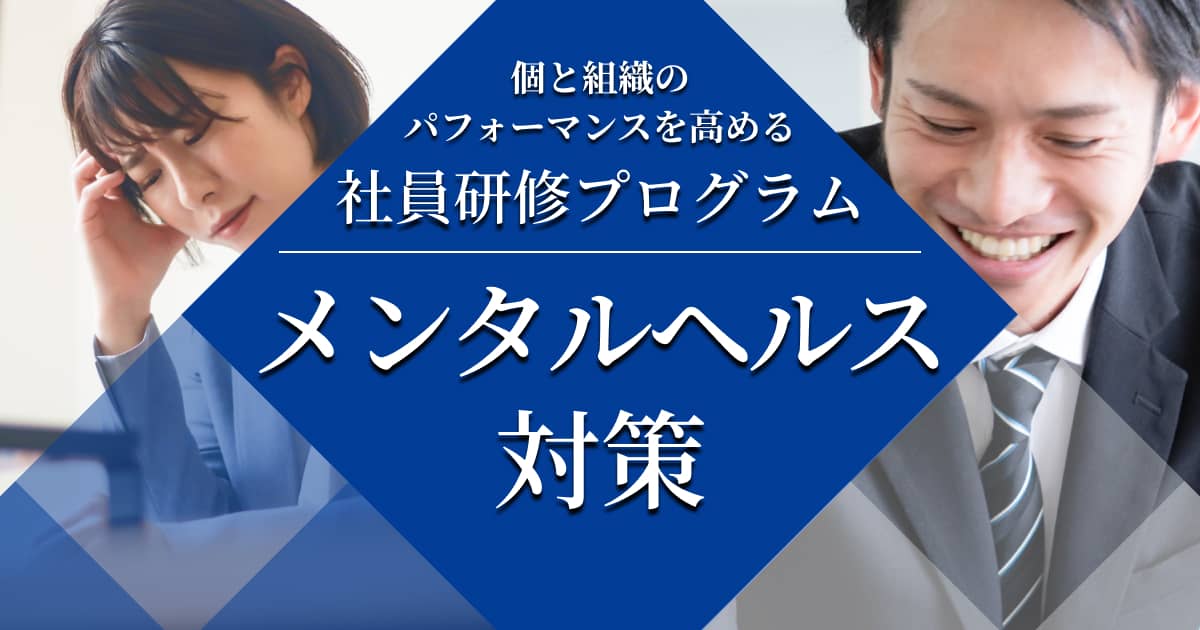職場の人間関係は、ストレスや離職の大きな要因です。本記事では、上司・同僚との関わりで生じる悩みの原因のほか、心身の健康と生産性を守るための「個人でできる対処法」や「企業・管理職が実践すべき改善策」を解説します。職場のストレス軽減と組織力向上を目指す方は必見です。
個人の努力だけでは解決が難しい職場の人間関係の課題には、企業や管理職による組織的なアプローチが欠かせません。「アドバンテッジ タフネス」は、ストレスチェックを起点に、組織全体での課題把握と改善をサポートするサービスです。従業員が安心して働ける環境の実現を支援します。
目次
職場の人間関係に悩む人は多い

職場の人間関係に悩みを抱えている人は、決して少なくありません。日本労働調査組合が過去に実施した調査では、6割近くの人が「人間関係を理由に退職や転職を検討したことがある」と回答しています。
また、厚生労働省の「令和6年度雇用動向調査」でも、男性の9.0%、女性11.7%が前職の離職理由を「職場の人間関係が良くなかった」と答えました。このように人間関係の悩みは、多くの職場で共通する離職要因になっていることがうかがえます。
参考:厚生労働省「令和6年 雇用動向調査結果の概要」
心理的ストレスは職場の人間関係で増えやすい

働くストレスの主な要因は「対人関係」「業務の量」「業務の質」の3つですが、特に人との関わりが大きな割合を占めます。心理学者のラザルスは、結婚や転職といったライフイベントよりも、デイリーハッスル(日常の小さな苛立ち)が心身への影響度において重要だと指摘しました。同僚の一言や作業の滞りなど、一見ささいな出来事も繰り返されると大きなストレスとなります。デイリーハッスルは自覚がないまま蓄積するため、「気づいたときには限界になっていた」というケースも少なくありません。
職場の人間関係に悩む原因

職場の人間関係は、人員配置の観点からも急な変化をもたらすことが難しいものです。ここでは、職場の人間関係に悩んでしまう原因を深掘りしていきます。
コミュニケーションが十分にできていない
コミュニケーションが不足し必要最低限のやり取りだけになると、情報共有が滞り、誤解やミスが増えるリスクが高まります。従業員からは「指示が不明確で仕事が進まない」「質問しづらい」といった悩みが生まれる可能性があります。また、言葉の選び方次第では意図せず相手にネガティブな感情を与え、それが原因でさらに会話が減る悪循環に陥ってしまうのです。
【関連コンテンツ】
コミュニケーションエラーとは?職場で発生する原因と対策
価値観や性格が合わない人がいる
価値観や性格の不一致は、職場での摩擦を生みやすい要因の一つです。世代間のギャップや、個々が育った環境の違いも、価値観のずれにつながりやすいでしょう。しかし、働くうえでは日常的に接する機会も多く、苦手な人とも協力しながら仕事を進めなければならないため、ストレスを抱えることになります。
業務量が多い/競争が強い
業務量が多く、過度な競争が行われる環境は、人間関係に問題を生じさせやすくなります。長時間労働などで疲労が蓄積するとイライラし、お互いを思いやる余裕がなくなり、職場の雰囲気は悪化しがちです。また、行き過ぎた成果主義のもとでは、同僚を「仲間」ではなく「ライバル」や「敵」として見てしまい、人間関係に支障をきたす可能性があります。
意見を自由に表明できない
意見を自由に表明できない環境が人間関係の悩みを深めています。意見が否定される経験が積み重なると、従業員は発言を避け、不満や建設的な意見を伝えられず、フラストレーションが蓄積します。さらに、「周囲との関わり方が評価される」という緊張感から本音が言えず、自分らしく振る舞えないストレスを感じることも大きな問題です。
ハラスメントが起きている
職場でのハラスメントは、人間関係を壊す典型的な例です。ハラスメントの被害を受けた本人だけでなく、目撃した周囲の人にとっても強いストレスを与え、苦痛を感じさせます。
ここまでに挙げた4つのケースも、職場で常態化しており、かつ度が過ぎるとハラスメントになり得ます。
【関連コンテンツ】
【ハラスメント】総まとめ!~意味から事例、取り組みのコツまで徹底解説
職場の人間関係を改善するメリット

職場の人間関係が改善されると、働きやすさを感じます。続いては、具体的なメリットを3つご紹介します。
ストレスが軽減され、安心して働ける
良好な人間関係と、職場の心理的安全性は相互に影響し合い、どちらも安心して働ける環境づくりに欠かせない要素です。声をかけるたびに緊張することもなく、相談や質問もしやすくなるでしょう。確認不足によるミスが減り、業務の効率が上がることも期待できます。
【関連コンテンツ】
心理的安全性とは?心理的安全性のメリットや心理的安全性の高い職場のつくり方を解説
自分の能力を十分に発揮でき、生産性が向上する
人間関係に悩んでいたり、遠慮があったりすると、本来の力を出し切れません。上司や同僚と良好な関係が築けていれば、自分のスキルや強みを発揮しながら、集中して仕事に取り組めます。仕事に対する前向きな気持ちは、「もっと成長したい」という意欲につながり、チームや職場にもポジティブな影響をもたらします。結果、職場全体の生産性向上が期待できるでしょう。
長く働き続けられるため、離職率が低下する
先述したように、職場の人間関係は退職の大きなきっかけとなりやすいです。人間関係が良好であると、仕事に楽しさややりがいを見出せ、「もっとこの仲間と頑張りたい」「この職場で働き続けたい」という思いを持ちやすくなります。長く働き続けることは、経済的な安定やキャリア形成の面でもメリットがあります。企業としても、離職率の低下は大きな利点です。
職場の人間関係に悩んだときの対処法【個人向け】
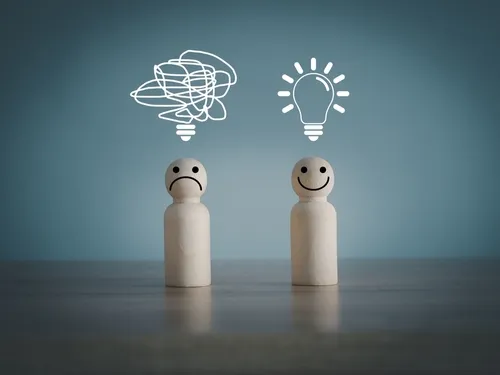
相手の行動や感情を変えることは、非常に難しいと言わざるを得ません。人間関係に悩んだときは、自分自身の考え方や行動を変えることによる対処に目を向けてみましょう。
困難な状況に直面した際、ネガティブな気持ちに流されず、問題解決のために行動できる能力をメンタルタフネスと言います。諦めて問題から逃げたり、感情的になったりする「マイナスの認知・行動」を「今できる対処」に転換し、問題を冷静に捉え直すことが大切です。問題解決につながる「プラスの認知・行動」を増やすと、ストレス耐性が高まり、人間関係の見え方も少しずつ変わっていくでしょう。
ここでは、メンタルタフネスを高めるための4つの視点から、人間関係のストレスとの向き合い方をご紹介します。
【関連コンテンツ】
メンタルタフネスとは?メンタルが強い人弱い人の特徴や高める方法についても解説
【前向きに考え直す行動】”思考のクセ”を改善する
人は他者を変えられなくても、自身の考え方や反応を変えることで状況の捉え方が大きく変わります。その第一歩は、誰にでもある「思考のクセ(認知の偏り)」に気づき、修正していくことです。
例えば、「何でも自分のせいにする」「~すべきという厳しいルールを課す」「根拠なく悲観的に決めつける」といった無意識の思考パターンを、まず自覚することが大切です。否定的なフィードバックを受けた際も、「自分はダメだ」とネガティブに捉えるのではなく、「指摘を直せば成長できる」と、前向きな思考パターンに変換しましょう。
【前向きに考え直す行動】見方を変える
多くの人が集まる組織では、価値観や性格が異なる人がいるのは当然のことであり、すべての人と良好な関係を築くのは難しいものです。無理に合わせようとすると、かえってストレスを抱え込んでしまうおそれもあります。見方を変えて、「嫌な人」ではなく「考え方が違う人」、「細かい人」ではなく「几帳面な人」と捉え直してみるのもおすすめです。言葉を変えるだけでも受け止め方が変わり、気持ちが少し楽になります。
【問題解決行動】適度な距離感を保つ
自分が心地よく過ごせる、ほど良い距離感で接することも大切です。特に新しい環境では、早く職場になじもうとして、必要以上に関わりすぎて疲れてしまう場合もあります。
敬語を使い、挨拶や仕事上のやり取りは行いながらも、プライベートな話題には深入りしない、必要以上に自分の情報は開示しないなどの工夫をしてみましょう。仕事を円滑に進めるための協力関係は築きつつ、一定の線引きをすることで、悩みを減らせます。
【問題解決行動】悩みから離れスキルアップに励む
悩みから意識的に離れる時間をつくりましょう。他人の評価を過度に気にしてしまう裏には、自分に自信が持てていないこともあります。勉強してスキルを磨いたり、新しいことに挑戦してみたりするのも有効です。身につけた知識や経験を仕事に活かせれば、職場の人間関係が良い方向に動く可能性もあります。
また、趣味や習い事などでプライベートの活動を広げ、熱中できることを見つけるのもおすすめです。職場の人間関係の悩みが相対的に小さく感じられるかもしれません。
【気分転換行動】セルフケアに取り組む
ストレスを溜めないためには、セルフケアが重要です。心身の回復に欠かせない十分な睡眠を確保し、規則正しい生活を心がけましょう。自分に合った方法で積極的に気分転換を行うことも大切です。社内では深呼吸やストレッチ、休憩中の飲食などでリラックスを。休日には散歩や趣味を楽しみ、自分にとって心地良いケアの継続が、効果的なストレス対策となります。
【関連コンテンツ】
メンタルヘルスにおけるセルフケアの重要性。職場や自宅でできるセルフケア方法やポイントを解説
オフィスで出来る!リラクセーション法(呼吸法)~ 心体パフォーマンスを高めよう ~
【相談行動】信頼できる人に悩みを相談する
職場の人間関係は、自分だけで解決するのが難しいケースもあります。その際は、信頼できる相手に悩みを相談してみるのも一つの方法です。相談相手は、悩みをどのように解消したいのか、目的に応じて考えることが大切です。
例えば、職場の環境改善を望むなら上司へ、第三者の意見を求めたいなら事情を知っている同僚へ、単に話を聞いてほしいときは、家族や友人でも良いでしょう。社内の人に相談するときは、愚痴や悪口と受け取られないよう伝え方の工夫が必要です。
管理職・企業が従業員同士の人間関係を改善するメリット

管理職や企業の人事担当者は、従業員同士の人間関係が改善に向かうよう努めましょう。職場の人間関係が良好になると、コミュニケーションロスや摩擦が減り、業務が効率化されます。また、心理的安全性が高まり失敗を許容する風土が生まれることで、新しい挑戦やイノベーションが促進されます。組織の活性化と企業の成長を後押しし、定着率向上による採用・教育コストの削減にもつながるのです。
管理職が職場の人間関係を改善するための取り組み方法
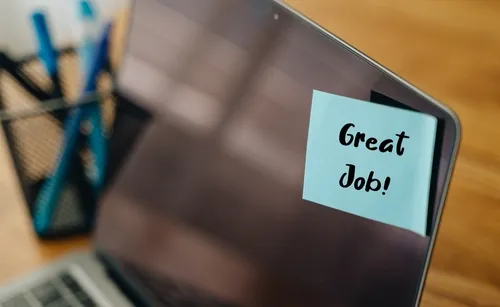
職場の人間関係をより良いものにしていくために、管理職ができる取り組みをご紹介します。
【関連コンテンツ】
風通しの良い職場とは?メリット・デメリットや、企業ができる具体施策を解説
個々に合わせたコミュニケーションを意識する
物事の捉え方や考え方は人それぞれであり、コミュニケーションが苦手な人もいれば、過剰に気を遣って疲れてしまいやすい人、ついネガティブに受け取りがちな思考を持つ人もいます。一人ひとりの性格や価値観を把握し、その人に合った関わり方で、悩みや不満を抱えていないか声をかけたり、部下から相談や報告がしやすい雰囲気をつくったりすることが重要です。
【関連コンテンツ】
理想的な「上司と部下の関係」とは?よい関係を築くためのコツや施策
ポジティブな言動を心がける
上司の言葉や態度は、職場全体の空気を左右します。管理職自身が意識的にポジティブな言動を心がけが大切です。「ありがとう」と一言添える、出退勤の挨拶を明るく返すなど、日常的な振る舞いが職場の人間関係を改善するきっかけになります。
定期的な面談の機会を設ける
職場の人間関係の悪化は、相互理解の不足が原因となることが多々あります。定期的な1on1を実施し、仕事や職場の悩みを丁寧に聞き取り改善につなげましょう。これにより部下は「上司が気にかけてくれている」と感じ、信頼関係が深まります。上司は聞き役に徹し、説教や自慢話は避け、部下が主体的に話せるようサポートすることを心がけます。
【関連コンテンツ】
1on1とは?ミーティングの進め方やオンラインでの注意点をご紹介
企業が職場の人間関係を改善するための取り組み方法

最後に、職場での人間関係改善のために、企業としてできる取り組みをご紹介します。
ストレスチェックやサーベイを実施し課題を早期に把握する
人間関係の不和は、一見個人の問題にも見えますが、実際には組織の風土や構造に起因することも少なくありません。ストレスチェックやサーベイを実施することで、現場が抱えるストレスや人間関係の不満を早期に把握できます。ストレスチェックの集団分析結果などをもとに対策を検討・実施し、その後も定期的にサーベイを行えば、施策の効果測定と変化の定点観測が可能となります。
コミュニケーションを活性化させる
良好な人間関係にはコミュニケーションが不可欠です。社内イベントやカフェスペース設置など、交流の機会を整え、相互理解を深めましょう。
リモートワーク環境では、雑談用のチャットスペースの開設や、スタンプなどの気軽なやり取り、定期的なウェブ会議を通じて「気にかけている」という気持ちを伝える工夫により、不足しがちなコミュニケーションを補うことが重要です。
悩みを相談できる窓口を用意する
社内の関係者などに事情を知られたくないと考える従業員もいるため、第三者に相談できる窓口を設置しましょう。窓口は誰でも気軽に利用できる、強いストレスを抱えて心身が不調に陥ってしまう前でも相談できる、相談の秘密は守られることを丁寧に周知し、活用を呼びかけます。相談できる環境を整えることは、早期解決だけでなく、メンタルヘルス対策や離職防止の観点からも重要です。
メンタルヘルスやストレス対処に関する研修を実施する
ストレスへの対処法や向き合い方、セルフケアを学ぶ機会を提供することも重要です。管理職向けには、ラインケアをはじめ、部下へのメンタルマネジメント指導をテーマとした研修も役に立つでしょう。
■管理職「メンタルヘルスマネジメント研修(ラインケア基礎)」「部下のメンタルタフネス度向上研修」など
■全従業員「メンタルタフネス度向上研修」「ストレスマネジメント研修(セルフケア)」など
良好な人間関係を築き、個と組織の成長を促進

職場の人間関係は、個人の心の健康や働きやすさだけでなく、組織全体の成果と成長に直結します。すべての人と良好な関係を築くのは難しくても、協力して仕事を進める上で、お互いを尊重し合う姿勢と適切なコミュニケーションは不可欠です。それぞれの立場から取り組みを行い、誰もが安心して働ける職場を実現しましょう。