風通しの良い職場とは、従業員同士のコミュニケーションが取りやすく、快適に働ける職場を指します。理想的な職場環境として語られることも多いですが、やや抽象的な印象を受けるかもしれません。では、「風通しの良い職場」にはどのような特徴があるのでしょうか。本記事では、風通しの良い職場のメリットやデメリット、企業が取り組むべき施策をご紹介します。
目次
風通しの良い職場とは?

「風通しの良い職場」とは、役職や立場によって発言を制限されず、それぞれの従業員が率直に自分の意見を発信できる職場のことです。ただし、好き勝手に発言して良いというものではなく、「一定の節度が保たれており、互いを尊重している」「心理的安全性が確保されている」ことが前提となります。風通しの良い職場は、”心理的安全性が高い職場”と言い換えることもできるでしょう。
風通しの良い職場の特徴

風通しの良い職場には、以下のような特徴があります。
積極的にコミュニケーションを取っている
風通しの良い職場は、従業員同士のコミュニケーションが積極的に取られています。円滑なやり取りが生まれており、年齢や立場、部署に関係なく従業員同士の連携も取れているのが特徴です。情報共有や報告・連絡・相談などが逐一行われている、仕事でわからないことや困りごと、トラブルが起きた際も臆することなく相談できる雰囲気があります。
また風通しの良い職場は、コミュニケーションの一環として挨拶が交わされていることも特徴です。誰もが明るく挨拶をしたり、挨拶を返すことで職場全体が活気に包まれたりすることで、話しやすい雰囲気が生まれます。従業員同士の交流も自然と深まり、気持ち良く仕事に取り組めるでしょう。
意見交換が活発である
風通しの良い職場は、意見交換が活発に行われており、忖度なしに自分の意見や提案を述べることができます。誰かに対して遠慮のない意見を出したとしても、それを責められることはなく、チームの人間関係にも影響しません。オープンに意見交換がなされることによって、さらにコミュニケーションが活性化します。
人間関係が良好である
風通しの良い職場は、従業員が年齢や役職、社歴に関係なく、相手を尊重する気持ちを持って接しているため、人間関係の摩擦が少なく良好な関係を築いています。フラットなコミュニケーションができていると、組織に団結力が生まれ、チームワークが発揮されたり、従業員同士が助け合ったりする雰囲気が醸成されます。
風通しの良い職場のメリット

風通しの良い職場は、従業員が快適に働けるだけではなく、企業にとってもさまざまなメリットがあります。ここでは、風通しの良い職場にすることで企業が得られるメリットをご紹介します。
生産性が上がる
風通しの良い職場は、コミュニケーションが盛んに行われているため、適切な役割分担や業務での連携が上手くいきます。従業員同士が意見交換を積極的に行うことで、課題や問題点の発見、アイディアやノウハウの共有がスムーズに行われます。
また、「上司に聞きづらくて進められない」「ミスを指摘すると機嫌を悪くされそう」といった状況も起こりづらいでしょう。業務に集中しやすい環境であるため、仕事が円滑に進み、生産性向上につながります。
離職率が低くなり従業員が定着する
従業員が離職を選択する大きな理由に「職場の人間関係」があります。2021年に日本労働調査組合が行った「仕事の退職動機に関する調査」では、「職場の人間関係、コミュニケーション」を退職理由に挙げた人が最も多くなりました(38.6%、同率1位)。
前述したように、風通しの良い職場は人間関係が良好に保たれているため、離職率低下や従業員の定着にも寄与します。お互いを信頼して仕事を進めることができるため、仕事に関する悩みや不満も解決しやすいでしょう。これは、従業員のモチベーションアップやエンゲージメントの向上にもつながります。
ミスが起きにくい
風通しの良い職場は、立場や役割に関係なくさまざまな情報共有がなされるため、情報の伝達不足や勘違い、認識の相違によるミスが起きにくくなります。また日頃からコミュニケーションが積極的に行われていることで、トラブルの予兆を早期に発見でき、ミスの未然防止にもつながります。
万が一、ミスが発生してしまった場合もすぐに報告できるため、ごまかしたり隠したりするようなことが起こらず、早急なフォロー・リカバリーの対応ができるでしょう。
新しいアイディアが生まれやすい
自分の意見が否定されず、受け入れられる環境がある職場では、多様な考えを述べやすく、新しいアイディアが生まれやすくなります。個々では気付けなかった課題や、改善につながるヒントを得られることもあるでしょう。部署を超え、さまざまな意見が集まることで、新規事業などのイノベーション創出も期待されます。
風通しの良い職場のデメリット
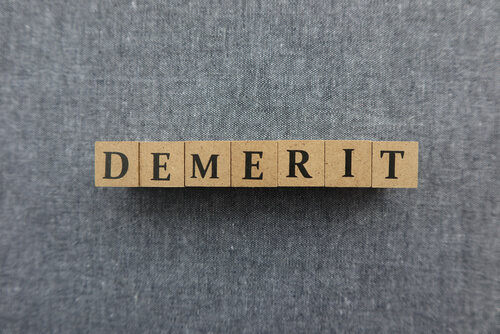
ご紹介してきたように、風通しの良い職場が実現されるとさまざまなメリットがありますが、適切に取り組みを進められないと、方向性を誤ってしまいデメリットが生じることがあります。続いては、風通しの良い職場のデメリットをご紹介します。
居心地の悪さを感じる人もいる
従業員の中には、積極的にコミュニケーションを取ることを苦手と感じる人もいます。オープンに意見を述べ合える職場環境にプレッシャーを感じ、かえってストレスになってしまう可能性もあります。
また、他の従業員が積極的に発言している姿に気後れし、居心地の悪さを感じる場合もあるでしょう。さまざまな性格の従業員がいることを理解した上で、コミュニケーションや発言を強要させることのないよう注意が必要です。
上司・部下の立場が曖昧になる
上司と部下の関係がフラットで、忖度なく自由に進言できる雰囲気が醸成されることは良いことですが、「何でも言っていいフラットな関係」を「友達感覚」のように解釈してしまうと、上司と部下の立場が曖昧になってしまいます。部下が指示を聞かない、自分勝手な振る舞いをする、といったトラブルが生じることもあります。
組織としての緊張感が失われる
一緒に仕事をするチーム、といった前提が失われ、単なる「仲良し集団」になってしまうと、組織としての緊張感が失われる可能性があります。ミスをしても「まあいいや」で片付けてしまう、約束や納期を守れない、業務に関係ないことばかり話すなど、勤務態度がルーズになってしまうこともあるでしょう。仕事とプライベートを切り分けてメリハリを付け、責任感を持って業務に取り組むことが大切です。
風通しの良い職場にするために企業ができる施策

風通しの良い職場を整えるためには、企業として取り組めることもあります。ここでは、企業ができる具体的な施策についてご紹介します。
社内アンケートやサーベイを実施する
風通しの良い職場づくりを進めるために、社内アンケートやサーベイを実施しましょう。人事が思い描く風通しの良い職場と、従業員が思い描く良い職場との間にギャップがあると、環境づくりは失敗に終わる可能性があります。「従業員は今の会社の雰囲気をどう感じているか」「コミュニケーションを取れていると感じるか」「職場環境に不満はあるか」など、組織の現状を把握することで、より満足度の高い環境を整えられます。
また、後述するメンター制度やジョブローテーションなど、各種施策の導入前にアンケートを行い、取り組みについての意見を募ることも有効です。

「アドバンテッジ ウェルビーイング DXP」は、メンタル・フィジカル・勤怠のデータを自由に掛け合わせて、目的に応じた分析が可能です。D&I観点での分析機能も標準搭載されており、課題把握や施策策定に役立てることができます。

「TOUGHNESS」×「pdCa」は、自社の課題把握と解決にお役立ていただける、サーベイを起点とするワンストップサービスです。従業員のメンタルヘルスやエンゲージメント状況をセンサスで定点観測し、課題に対する施策効果をパルスサーベイで迅速に検証します。
「アドバンテッジ タフネス」の指標や基準に合わせて構築したパルスサーベイ「pdCa」を活用することにより、比較が容易となり、前後の変化も捉えやすくなります。課題解決が進まない原因となっていた「測りっぱなし」「やりっぱなし」を解消します。
従業員向け研修を行う

お互いを尊重し、意見を言いやすい環境づくりや、部署やチーム内で円滑なコミュニケーションが取れるようになることを目的に、チームビルディングの観点から取り組みを進めることも効果的です。例えば、新入社員や若手社員に向けては同僚との関係構築によりスムーズな業務の遂行を目指す、管理職に対してはマネジメントスキルの育成などを重視した各種研修を行います。

アドバンテッジリスクマネジメントが提供するEQ向上研修は、リーダーシップの向上やハラスメント防止だけでなく、組織全体のマネジメントを円滑にすることにもつながります。そして、組織の生産性を向上させることも期待できるでしょう。研修を管理職が受講したところ、該当部署のストレスチェックの結果が大きく改善、従業員全体の意欲が向上し、活気に満ちた職場に変わったという企業もあります。
1on1ミーティングを実施する
「1on1ミーティング」は、上司と部下が1対1で行う面談で、業務の成果や今後の目標などについて話し合うものです。上司は聴き役に徹し、部下は日頃考えていることや悩み、今後のキャリアなどについて話します。向かい合って会話をする時間を設けることで、課題発見につながるだけではなく、上司にとっても部下と向き合う心構えができたり、これまで気づかなかった部下の考えを知ることができたりするため、サポートしやすくなります。お互いの思考を整理し共有すれば、信頼関係の構築にもつながるでしょう。
実際に、週1回30分ほどの1on1ミーティングを取り入れた企業では、上司と部下のコミュニケーションや部下のマネジメントなどに効果を発揮しているという例もあります。
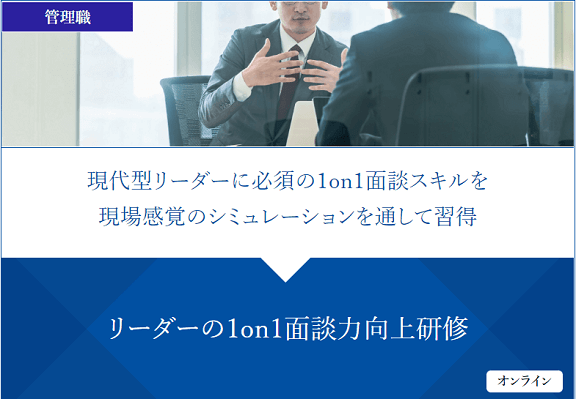
アドバンテッジリスクマネジメントでは、上司と部下が1対1で面談を行う「1on1」の実践ノウハウを身に付ける研修をご用意しています。変化の激しい現代で成果を挙げる「優れたリーダーの条件」について、模擬体験やロールプレイを通して、現代型リーダーシップ行動としての1on1のノウハウを習得します。詳しくはこちら。
メンター制度を導入する
メンター制度とは、豊富な知識と経験を持つ先輩社員が、後輩社員(主に新入社員)に対し、仕事の相談に乗ってアドバイスしたり、問題解決をサポートしたりする制度です。入社したばかりで不安を抱える新入社員にとって、何でも話せるメンターは心強い存在となり得ます。メンターを務めるのは、上司・部下の関係になく、年齢や社歴が近い先輩社員が選ばれるのが一般的です。
ジョブローテーション・社内留学制度を設ける
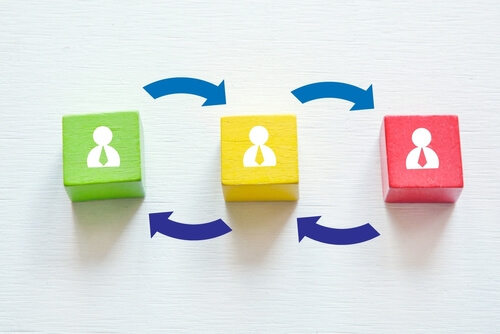
ジョブローテーションとは、半年~1年程度のスパンで定期的に部署異動、職務変更を行い、さまざまな業務を経験する制度です。一方、社内留学とは自身が勤務している部署とは異なる部署で、一定期間仕事を体験するものです。
多様な業務を経験することで、従業員の視野が広がるだけではなく、人脈づくりにも貢献するため、部署や部門の垣根を越えたコミュニケーションが実現します。
社内用コミュニケーションツールを導入する
チャットや、社内SNSなど、社内で使えるコミュニケーションツールを導入するのも、風通しの良い職場にするために効果的です。他拠点やリモートワークの従業員ともコミュニケーションが取りやすくなります。また、対面のコミュニケーションに苦手意識を持っている従業員でも意見を述べやすい環境が構築できます。
フリーアドレス制を導入する
職場で固定の席を決めないフリーアドレス制を導入すると、自然と多くの人との交流が生まれます。毎日異なる人と会話がしやすいだけではなく、デスク間の仕切りも設けられていないことが多いため、よりコミュニケーションが取りやすい雰囲気になるでしょう。部署の垣根を超えたコミュニケーションによって風通しが良くなり、新鮮な発想が生まれるかもしれません。
挨拶を習慣付ける
挨拶は基本的なコミュニケーションの1つです。挨拶を交わすことは、お互いに相手の存在を認識している、認めている、というメッセージになります。またお互いの存在を認めること(相互承認)で、心理的安全性が確保されるため、自然とほかのコミュニケーションも取りやすくなります。企業全体で習慣付けるためには、上司・先輩など、上の立場の人が率先して挨拶を行いましょう。
風通しの良い職場にするための注意点

風通しの良い職場づくりを成功させるために、意識すべきことがいくつかあります。ここでは、風通しの良い職場づくりを進める上での注意点を解説します。
従業員全員が快適に感じられる環境づくりを意識する
従業員の全員がコミュニケーションを得意としているタイプとは限らず、苦手と感じる場合があるかもしれません。苦手意識がある従業員を無視するような形で、コミュニケーションの活発化を目指してしまうと、そのような人にとっては逆に居心地の悪い職場となってしまいます。多様なタイプの従業員がいることに留意した上で、皆にとって風通しの良い職場を考えましょう。
メリハリのない職場にならないよう気を付ける
上下関係がない・言いたいことが言える・従業員同士の仲が良い、このような環境を目指したいところですが、度が過ぎるとメリハリのない状況になってしまいます。ルーズな組織では生産性が上がらないため、ある程度の緊張感は必要です。メリハリがない職場にならないよう、仕事をする場であること、目指す理想像を明確にした上で、締めるところはしっかり締めましょう。
風通しの良い職場を意識すべきサイン

最後に、風通しの悪い職場になっている可能性に気付きやすい社内のサインをご紹介します。人事担当など企業の担当者で、気になることがある場合には速やかに調べてみてはいかがでしょうか。
退職者が増加傾向にある
離職率が高い職場は、風通しに問題がある可能性が高いといえます。退職の理由として多いのは、「人間関係」「キャリアアップの不透明さ」「業務への不満」「待遇への不満」などです。どれも社内のコミュニケーションが取れていれば、改善できる可能性のある問題です。このような不満を抱え退職する場合、職場の風通しが良くないというサインですので、早急に対応策を考えましょう。
長時間勤務する従業員が増加傾向にある
長時間勤務をする従業員が増えている場合も、風通しに問題が発生している可能性があります。長時間働かなければならない原因として「業務の割り振りが上手くできていない」「連携が取れていない」「効率的に業務が進められていない」などが考えられます。
これらの問題を解消するには、従業員同士のコミュニケーションの活性化を図ることが大切です。長時間勤務は離職につながる可能性が高いため、速やかに対処しましょう。
風通しの良い職場づくりで魅力的な企業に

風通しの良い職場では、従業員がお互いを尊重し合いながら、活発なコミュニケーションが行われています。従業員がウェルビーイングな状態になれば、生産性の向上や離職率の低下、アイディア創出など、企業にとっても大きなメリットが得られるかもしれません。風通しの良い職場づくりの施策には、さまざまなものがあります。まずは、従業員サーベイを実施して現状を把握し、自社に適した施策を打ち出しましょう。




