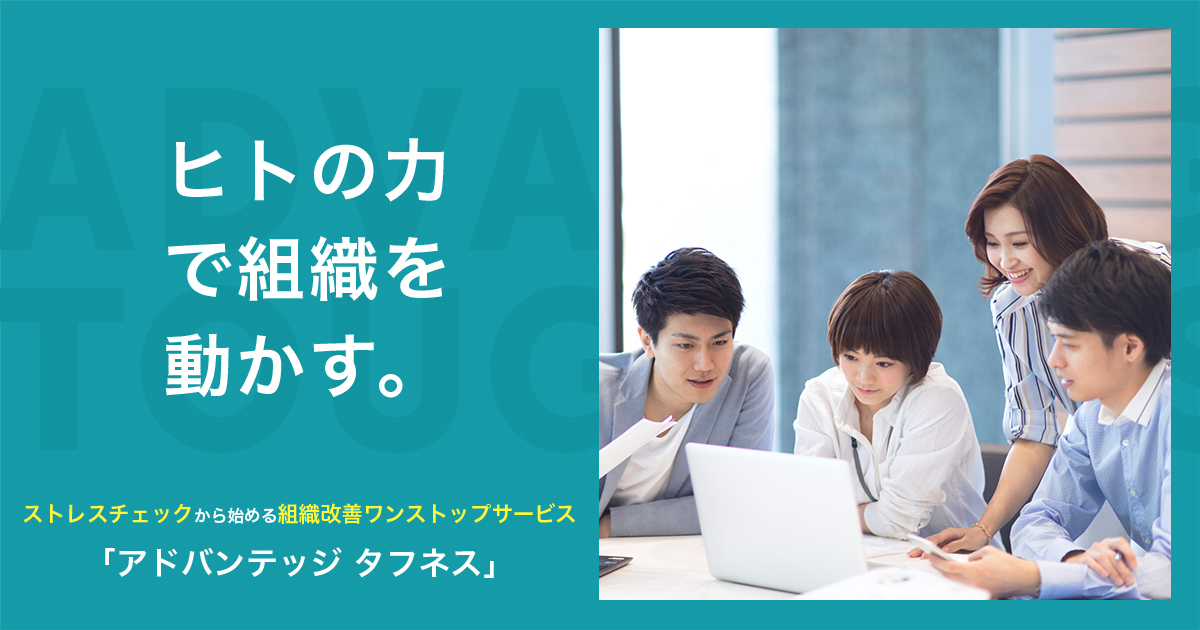昨今、「ワークライフバランスはもう古い」という指摘があります。しかし、仕事と私生活の両立や、柔軟な働き方といったワードには、現在も高い関心が寄せられています。本記事では、「ワークライフバランスが古い」と言われる理由と、ワークライフバランスに代わって注目されつつある「ワークライフインテグレーション」の概念について詳しく解説します。
休業者情報の一元管理サービス「ADVANTAGE HARMONY」は、育児・介護・治療などのライフイベントと仕事の両立を支援し、人事担当者の負担を軽減。組織全体の「働きやすさ」と「生産性向上」の実現に貢献します。
目次
ワークライフバランスとは
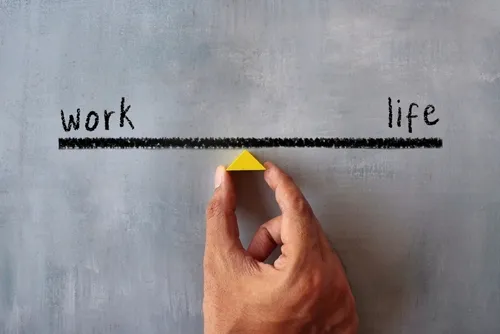
はじめに、ワークライフバランスとは何か、ワークライフバランス憲章を踏まえた現代の状況について整理していきます。
ワークライフバランスとは
ワークライフバランスとは、「仕事と生活の調和」を意味します。仕事と、育児・趣味などの個人生活を両立させる概念です。これは必ずしも「プライベート優先」ということではなく、一人ひとりが仕事と私生活のバランスに納得し、自分らしい生き方を実現できる状態を指します。性別や年齢、ライフステージの変化に関わらず、個人の価値観が尊重されることがもっとも重要です。
【関連コンテンツ】
ワークライフバランスとは?取り組み推進のメリットや企業事例
ワークライフバランス憲章策定当時と現在の変化
国が2007年に策定した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では、ワークライフバランスが実現した社会を以下のように示しました。
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」
この理想を実現するための3つの柱および行動指針は、以下の通りです。
- 就労による経済的自立の実現:すべての人が安定して働ける環境
- 健康で豊かな生活を送るための時間確保:長時間労働の是正と休暇取得の促進
- 多様な働き方・生き方の選択:育児や介護など、ライフステージに応じた柔軟な働き方
これらは、今なお重要な指針である一方で、制度面の整備が進んだ現在では、新たな課題や多様な価値観が生まれています。当時のワークライフバランス憲章が示した理想を“次の段階”へ発展させる、新しい概念が求められているのです。
参考:「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
ワークライフバランスは古いと言われる3つの理由

働き方改革の浸透とともに、ワークライフバランスという言葉そのものも定着してきました。一方で、時代や働き方が変化するにつれ、ワークライフバランスの考え方そのものを「古い」と指摘する声もあります。ここでは、その理由を3つの視点で解説します。
ワークライフバランスに対する誤認識が浸透している
ワークライフバランスには、「仕事と生活を天秤にかけて調整する」という誤解が存在します。かつて長時間労働が中心だったため、ワークライフバランスは「労働時間を減らすこと」と解釈が広まりました。その結果、業務効率化がなされないまま時短が求められ、かえって従業員の負担が増すケースもみられました。
単に時短や休暇取得という「手段」に目が向いてしまい、この根本的な目的が置き去りになりがちですが、本来の目的は、仕事と私生活の両方で充実感を得て、多様な生き方を実現することです。
多様な働き方への対応が進んでいる
テクノロジーの進歩やリモートワークの普及により、「オフィスに出社し定時まで働く」以外の柔軟な働き方が一般化しています。これにより、「仕事か私生活か」の二者択一ではなく、グラデーションのようにそれぞれが入り混じるようになりました。そのため、「どちらを優先するか」を前提とする従来のワークライフバランスの考え方は、現状の多様な働き方や個々のライフスタイルに合わなくなりつつあります。
「ワークライフバランス」の概念が拡大している
残業規制や有給休暇取得の義務化によって、一定の「時間的なゆとり」は得やすくなりました。しかし、先述のようなリモートワークの普及や、副業や兼業を許可する企業が増えたことで、一層生活の中に仕事が複雑に入り込むようになっています。
ワークライフバランスは、これまでのように「仕事と生活の時間配分を考え、バランスをとる」発想から、「個人の生き方」や「キャリア観」など、「自分らしい働き方」を考える方向へシフトしつつあります。そのため、従来のワークライフバランスの枠組みを超えた、新しい考え方が求められているのです。
参考:「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
参考:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
ワークライフバランスの現状と、新しい働き方の可能性
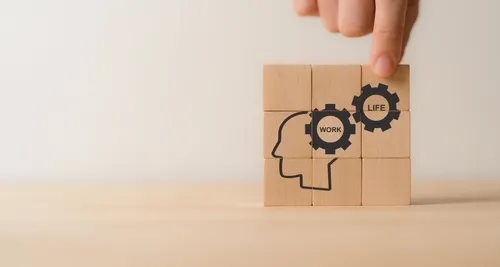
国や企業は、ワークライフバランスの実現に向けた取り組みに力を入れていますが、なかなか実感を抱きにくい人もいるのではないでしょうか。続いては、データをもとにワークライフバランスの現状を分析します。
ワークライフバランスの現状
国は、先述した「仕事と生活の調和が実現した社会」を目指し、行動指針を策定した中で、15の項目について具体的な数値目標を掲げて取り組みを推進していました。このうち、国が「ほぼ達成」または「達成」と判断したのは15項目中わずか4項目のみにとどまっています。
【ほぼ達成/達成とした項目】
- 週労働時間60時間以上の雇用者の割合
- 認可保育所等(3歳未満児)
- 放課後児童クラブ
- 就業率
長時間労働の是正や就労機会の拡大という点では一定の成果がみられましたが、未達成の指標も多く、実現の道のりは半ばと言わざるを得ません。その背景には、企業文化として従来の慣習が根強く残っていること、新しい働き方が導入されても一部の従業員のみが対象となり、浸透していないことなどが指摘されています。
ワークライフバランスの実現は依然として厳しい状況です。調査では、子育て世代を中心に「仕事と家庭の時間をバランス良く持ちたい」という理想と現実の間に大きな隔たりがあることが示されています。既婚・未婚を問わず、誰もがライフステージに応じて柔軟に働き方を選べる環境づくりが、今、強く求められています。
参考:内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)総括文書 –2007~2020–」
参考:内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する参考統計データ」
新しい働き方への期待と課題
一人ひとりが望む多様な働き方を実現していくためには、より幅広い取り組みが求められます。そこで注目されているのが、仕事と私生活を切り分けて捉えるのではなく、「調和」を目指す新しい視点です。
ライフスタイル全体の充実が従業員のモチベーション向上につながり、能力を最大限に発揮することで、企業も生産性向上のメリットを得られます。ただし、成功には従業員の主体的な働き方と、企業側の抜本的な制度見直し、環境整備が不可欠です。
【関連コンテンツ】
仕事におけるモチベーションとは?上がらない原因や従業員のモチベーションを上げる方法を解説
ワークライフバランスに代わる考え方「ワークライフインテグレーション」とは

近年、ワークライフバランスにまつわる新しい概念として「ワークライフインテグレーション」という考え方が広がりつつあります。ワークライフインテグレーションの意味や定義、似た概念との違いについてご紹介します。
ワークライフインテグレーションとは
ワークライフインテグレーションとは、仕事(ワーク)と私生活(ライフ)を対立させるのではなく、相互に良い影響を与え合う要素として統合(インテグレーション)して捉える新しい考え方です。従来のワークライフバランスが「どちらを優先するか」「一時的に調整する」というニュアンスが強かったのに対し、インテグレーションは人生の経験すべてが仕事に活かされ、仕事の経験も生活を豊かにするものとして捉えます。
これにより、育児や介護といった特定のイベント時だけでなく、常に両者が相乗効果を生み出し、人生全体の質(QOL)を高めることが期待されます。これは「ワーク・ライフ・バランス憲章」が目指す社会をさらに進化させる可能性を秘めているのです。
ワークライフインテグレーションとワークインライフ/ワークアズライフの違い
「仕事と私生活の関係性」をめぐっては、ワークライフインテグレーション以外にも、さまざまな概念が存在します。特に近い考え方である「ワークインライフ」と「ワークアズライフ」との違いを整理しておきましょう。
【ワークインライフ】
「ワークインライフ」とは、ライフ(人生)を基盤に置き、その中にワーク(仕事)が自然に含まれている、という考え方です。自分の人生(生き方)がまずあり、その中に仕事があるイメージです。
【ワークアズライフ】
「ワークアズライフ」とは、仕事とプライベートを明確に切り分けない考え方です。仕事を「生計を立てるだけでなく、自己表現や成長、充実感をもたらし、人生全体を充実させるもの」として捉え、人生の一部として、他のものと境目なく存在させます。
仕事と私生活を等しく大切な要素と捉え、「統合する」点にフォーカスされているのがワークライフインテグレーションに対し、ワークインライフは、「人生」に重きを置いています。ワークアズライフは、仕事と生活が溶け合って一体化していることが特徴です。
ワークライフインテグレーションの企業事例と成功ポイント
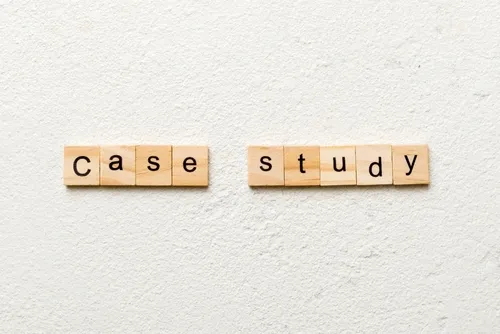
続いては、ワークライフインテグレーションに取り組む企業の事例と成功ポイントをご紹介します。
【男性の育児休業取得】積水ハウス株式会社
積水ハウス株式会社は、男性育児休業の取得を後押しするため、制度の個別周知や意向確認、相談窓口の設置といった環境整備を徹底しました。当初低調だった取得率は、これらの施策と、社長自らが登壇したフォーラムでの意識改革の結果、1年で約38%から約85%に大幅に向上。育休と在宅・フレックスを組み合わせることで、仕事と家庭の両立を実現しています。
参考:内閣府「全ての人が活躍できる働き方の推進に向けた事例集」
【月1の週休3日制を導入】株式会社健新
不動産業の株式会社健新は、休暇拡充として月1回の週休3日制を段階的に導入しました。これと並行し、タイムマネジメント研修やITツールの活用で業務効率化を徹底。その結果、残業時間の大幅な削減と、3年連続前年比130%の業績達成に成功しました。制度導入だけでなく、ソフト/ハード両面から浸透を図ったことが、ブランドイメージ向上と採用応募者の増加につながっています。
参考:内閣府「全ての人が活躍できる働き方の推進に向けた事例集」
【周囲への支援】中国水工株式会社
総合建設の中国水工株式会社は、育児・短時間勤務制度の整備に加え、組織的に欠員を補う仕組みを導入しました。具体的には、他部署からの異動と業務マニュアルでスムーズな引き継ぎを実現。さらにシステム開発で業務効率化を進め、周囲に負担が集中しない体制を構築しました。この「欠員を補う」視点の仕組みにより、制度が利用しやすくなり、互いに助け合う文化の浸透につながっています。
参考:内閣府「全ての人が活躍できる働き方の推進に向けた事例集」
企業がワークライフインテグレーションを取り入れる際の注意点

ワークライフインテグレーションは「仕事と生活の調和」を目指すものですが、企業による「両立支援」はその調和を実現するための“土台”にあたります。制度や仕組みが整っていなければ、従業員は安心して働き続けられません。最後に、企業がワークライフインテグレーションを取り入れる際の注意点をチェックしておきましょう。
【関連コンテンツ】
女性活躍推進法に基づく企業が取り組むべき両立支援のご紹介
制度への理解を深め、利用しやすい組織風土をつくる
ワークライフインテグレーションを取り入れるためには、制度の導入だけでなく、「利用しやすい雰囲気」づくりが不可欠です。経営層や管理職が率先して制度を活用し、本気度を示すことで「使うのが当たり前」という空気を醸成できます。また、部署内で積極的なコミュニケーションをとり、互いの事情を理解することで協力体制が築きやすくなります。併せて、評価やキャリア機会に差が出ないよう、評価制度の見直しも重要です。
ITツールを活用する
ワークライフインテグレーションを実現するうえでは、制度設計とともに業務効率化や人員不足への対応が欠かせません。まずは既存のITツールを活用し、スモールスタートすることで導入のハードルやコストを下げられます。チャットツールや自動化ツール、管理システムなどは、作業効率の向上が期待できるだけでなく、場所にとらわれない働き方の実現にも寄与します。
企業の両立支援や健康経営、DEI推進を支え、真のワークライフインテグレーションの実現を後押しします。
【関連コンテンツ】
ニューノーマルな働き方を実現させるためになぜDXが必要なのか
中長期的な視点で取り組み、見直しと改善を継続する
多様な働き方の実現に向けては、中長期的な視点を持つことが不可欠です。試行と改善を重ねる中で、自社に合う形が見えてくることも多いでしょう。段階的に始めて、課題が見つかればその都度改善し、制度を定着させていくのが望ましいです。併せて、ストレスチェックなどを活用し、働きやすさや柔軟な働き方の実現状況について問いかけ、従業員のニーズとマッチしているかを確認することも必要です。
時代や社会の変化に合わせ「新しい概念」へアップデート

「ワークライフバランス」から、仕事と私生活を相互に支え合う「ワークライフインテグレーション」への移行は、これからの働き方を考えるうえで重要なテーマです。制度を整えるだけでなく、「活用しやすい制度」として運用していくことが、本質的な実現を後押しします。従業員が自分らしく働き、人生を豊かにできる環境づくりを通じて、従業員と企業双方の成長につなげましょう。