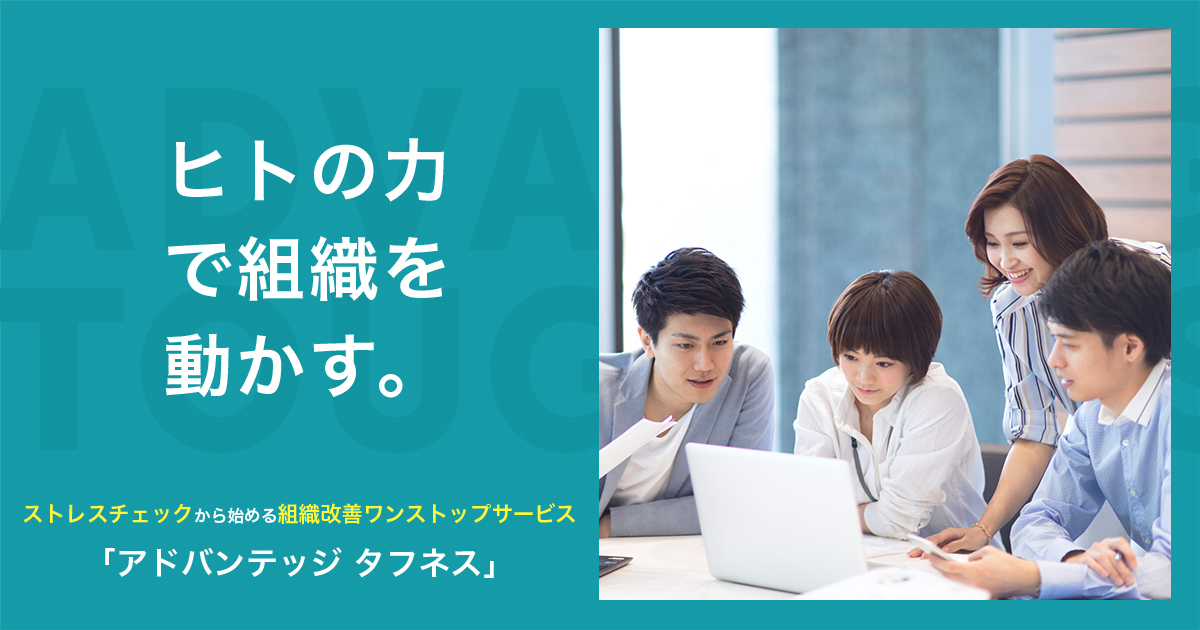従業員の健康状態は組織の生産性にも大きな影響を与えかねません。健康経営推進の動きが広がるとともに、「プレゼンティーイズム」や「アブセンティーイズム」への注目も高まっており、予防・改善のための取り組みはますます重要なものとなっています。本記事では、アブセンティーイズムの定義や要因、測定方法、企業ができる防止策について詳しく解説します。
目次
アブセンティーイズムとは

はじめに、アブセンティーイズムの定義について整理しておきましょう。
アブセンティーイズムとは
アブセンティーイズムとは、「健康上の理由により仕事を休んでいる状態(病欠)」のことです。WHO(世界保健機関)が、「健康問題に起因したパフォーマンスの損失」を示す指標の1つとして提唱しているものです。欠勤・休職のほか、遅刻・早退なども含まれます。
アブセンティーイズムは、健康経営のアウトカム指標の1つとしても用いられています。健康経営の取り組みによって従業員の健康意識や行動が改善されれば、アブセンティーイズムは減少し、従業員のパフォーマンスや業績の向上にも結びつくことが報告されているのです。
従業員の欠勤や休職が増えると、その分の労働損失や代替人員の確保コストが発生し、企業の生産性や業績にも影響します。アブセンティーイズム防止をはじめとした健康経営の取り組みは、企業の持続的な成長を支えるうえでも重要です。
プレゼンティーイズムとの違い

プレゼンティーイズムは、欠勤には至らないものの、従業員が心身の不調を抱えながら働いている状態を指します。アブセンティーイズムとの大きな違いは、「出勤できているかどうか」です。
プレゼンティーイズムの状態では、十分なパフォーマンスが発揮できないものの、アブセンティーイズムのように仕事を休んでいる状態ではないため、生産性の低下などの影響が可視化されづらいことが特徴です。プレゼンティーイズムの状態が長く続き、健康状態が悪化すれば、アブセンティーイズム(欠勤)に至る可能性があります。どちらかだけを対策するのではなく、「つながりのある1つの概念」として認識し、総合的な取り組みを行っていくことが大切です。
アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムに至る理由

アブセンティーイズムおよびプレゼンティーイズムは、心身の不調によって生じるものです。具体的な例は以下の通りです。
【身体的な不調の例】
- 風邪、感染症
- 頭痛、腹痛、胃痛
- 花粉症
- 怪我
- 慢性的な病気
- 月経・月経前症候群 ほか
【精神的な不調の例】
- 気分障害(うつ病など)
- 不安障害(パニック障害など)
- 自律神経失調症 ほか
アブセンティーイズムが企業に与える影響

次に、アブセンティーイズムが企業に与える影響についてみていきましょう。業界・職種を問わず人材確保が難しくなりつつある今、従業員が心身の不調によって欠勤・休職に至ってしまうことは多くの企業にとって痛手です。アブセンティーイズムに起因する問題を早期に解決しなければ、さらなる悪循環に陥りかねません。
業務の停滞・遅延が生じ生産性が低下する
従業員が欠勤すると、担当する業務がストップしてしまうこともあります。納期の遅延やサービスの質が落ちることが懸念されるほか、フォローに入るほかの従業員の業務のスケジュールにも影響してしまう可能性も考えられます。全体的な生産性や業務効率の低下につながりかねません。
他の従業員の負担が増える
欠勤者が発生すると、その従業員の業務をカバーする必要が生じ、同じ部署やチームのメンバーの負担が増えてしまいます。特に小売業や製造業、運輸業などは、交代要員の確保が難しいと負担が大きくなりやすいです。長時間残業や休日出勤などが続けば、慢性的な過労に至り、ミスが増えたり、労働災害を引き起こしたりするリスクも高まります。
コストが増える
欠勤に関連してさまざまなコストが発生することも懸念点です。医療費負担の増加やフォローに入る従業員の残業代増加、欠員補充のための採用・育成コストなどが挙げられます。
モチベーション低下・離職につながる
人手不足の状態が続き、周囲の従業員の業務負担が改善されなければ、「人手不足なのに企業は何もしてくれない」「自分ばかり負担が多い」と不満を募らせ、モチベーションが低下してしまいます。心身の疲労やストレスからメンタルヘルス不調に陥る可能性もあるでしょう。「もう耐えられない」と判断すると、離職を選択してしまうおそれもあります。
アブセンティーイズムによる企業の損失額はどのくらい?

アブセンティーイズムによる企業の損失額は、以下の計算で求められます。
【損失額=アブセンティーイズムによる欠勤日数×総報酬日額】
研究では、国内中小企業でのアブセンティーイズムの平均日数を2.6日と算出したデータも報告されています。概算で1人あたり2.6日×人件費分の損失が生じていることになるのです。また、企業の健康に関連するコストのうち約5%がアブセンティーイズムによるものと示された調査もあります。
参考:「中小企業における労働生産性の損失とその影響要因に関する研究」
参考:「健康経営ガイドブック(P36)」
アブセンティーイズムの測定方法

アブセンティーイズムを測定する方法は、主に3つあります。それぞれの実施方法と特徴を押さえておきましょう。
参考:「健康経営ガイドブック(P37)」
欠勤・休職データの取得
企業が保有している勤怠データを用いて算出もできます。疾病欠勤、休職の日数や回数を集計し、アブセンティーイズムの代替指標とします。既存のデータを活用できるため、導入のハードルが低いことがメリットです。ただし、年次有給休暇を療養に充てたケースは把握しづらいため、アブセンティーイズムが低く算出される可能性があります。
従業員へのアンケート実施
アブセンティーイズムでの欠勤の実態を把握するため、従業員にアンケートを取る方法もあります。「昨年の1年間のうち、自分の病気や体調不良のために仕事を休んだ日が何日ありましたか」という自己申告式の設問を設定します。年に1回のストレスチェックの際に独自項目として設問を設け、病欠の有無や日数を把握しましょう。
この方法では、病休や欠勤だけでなく、自身の体調不良のために年次有給休暇を使って休んだケースも含めて可視化できます。勤怠データではカウントされないアブセンティーイズムを補足できるため、より実態に近いデータが得られる可能性があります。ただし、アンケートの回収率や回答の精度によって結果が左右される点に注意が必要です。
休職者数・休職期間の把握
長期的に働けなくなり、休職している従業員の人数や休職期間も指標の1つとなります。長期の休職の場合、従業員に診断書の提出を求めているケースが多いため、休職の理由や期間を正確に把握しやすいです。ただし、休職に至らない程度の軽度な不調や、風邪や感染症などの短期間で改善する病気による欠勤までは反映されないため、他の方法とも併用が望ましいです。
アブセンティーイズムに関する取り組み例

続いては、アブセンティーイズムの防止にもつながる、従業員の健康支援に関する取り組み事例をご紹介します。
日本電信電話株式会社(現:NTT株式会社)
日本電信電話株式会社(現:NTT株式会社)は、メンタルヘルス不調による休務者が多いことを課題としていました。そこで、メンタルヘルス不調の早期発見、早期対応を促すべくパルスサーベイを実施。また、従業員が自分自身の健康情報を一元的に把握できるよう、ストレスチェックデータ等をデータ化するシステムを導入しました。ストレス関連疾患の発生予防と健康意識改善の取り組みが、各種指標の改善につながっています。
参考:健康経営 先進企業事例集
三菱地所株式会社
三菱地所株式会社は、従業員が心身ともに健康な状態で、最高のパフォーマンスを発揮しながら働き続けられるよう、アブセンティーイズムやプレゼンティーイズムのリスク低減に取り組んでいます。健康な体づくりを目指す社内イベントを実施したり、健康リスクの高い従業員への受診勧奨を積極的に行ったりすることで、健康経営の重要性についての認識が広がっています。
参考:健康経営 先進企業事例集
株式会社弘
株式会社弘では、歯科検診の費用補助やがん早期発見セミナーなどを実施し、従業員の健康支援を行っています。また、普段の自分自身の体調と今日の調子を比較し、把握できる計測デバイスを設置し、従業員に体調に応じた対処を考えてもらうためのサポートとして活用しています。
参考:健康経営優良法人取り組み事例集
アブセンティーイズムを防ぐために企業ができる対策

従業員のアブセンティーイズムを防ぐには、企業側からの積極的な支援が欠かせません。最後に、アブセンティーイズム対策として有効な取り組みを解説します。
健康診断の受診呼びかけ・サーベイの実施
欠勤・休職に至った後の対応も重要ですが、まずはアブセンティーイズムに進行しないための対策として、プレゼンティーイズムの予防が大切です。健康診断の受診を呼びかけ、従業員本人と企業双方に健康状態の把握・管理を行ってもらいます。
2次検査が必要になった従業員など、健康リスクの高い人にはさらにフォローを強化します。同時に、年に1回のストレスチェックや定期的なパルスサーベイの実施を通して、プレゼンティーイズム・アブセンティーイズムの把握と定点観測につとめましょう。
セルフケアの支援
従業員自身が心身の不調を早めに自覚し、適切に対処できるようにするためにセルフケアの支援を行いましょう。セルフケアについて学び、正しい知識を身につけるセミナーや、生活習慣改善を促すeラーニングの実施、健康情報の発信などを通して、健康リテラシーを高めることが大切です。セミナーはすべての従業員を対象に、定期的に実施します。また、勤務中に体を動かす時間を設ける、スポーツイベントを開催するなど、心身をリフレッシュする機会を設けることも1つの方法です。
ワークライフバランスの推進
長時間労働など、過度な業務負担が心身の不調を引き起こし、アブセンティーイズムに至ることもあります。残業時間を減らす取り組みのほか、リモートワーク、コアタイムなどの柔軟な勤務制度の整備を通して、従業員が体調やライフスタイルに合わせた働き方ができる環境をつくりましょう。休みやすい風土を醸成し、心身の回復・リフレッシュを促すことも、欠勤や休職のリスク低下につながります。
ラインケアの強化
プレゼンティーイズムやアブセンティーイズムの予兆をいち早くキャッチするには、日常的に従業員と接する管理職の心がけも重要です。ラインケアとは、上司が部下の心身の状態を気にかけ、必要に応じて適切なサポートを行うことです。
管理職に対してメンタルヘルスに関する知識や、部下の変化に早めに気づくためのポイントを伝えるラインケア研修を実施しましょう。また、1on1などコミュニケーションの機会を意識的に設け、周囲が心身の不調に早急に気づけるようにすることもアブセンティーイズムの未然予防に寄与します。
カウンセリング窓口の設置

産業医面談や保健師面談など、法律に基づく産業保健体制を構築し、従業員が自分自身の不調を相談できる機会を整え、早期にサポートを受けられるようにします。加えて、職場や仕事に関する悩み、プライベートに関する悩みなどを気軽に相談できるカウンセリング窓口を設けて、匿名で利用したい、気軽に相談したいというニーズの受け皿をつくります。窓口は誰でも利用できる、相談の秘密は守られることなどを周知しましょう。
アブセンティーイズムを防ぎ”健康な組織”へ

健康関連コストの増加をもたらすアブセンティーイズムは、企業にとって無視することのできないリスクです。個人の問題として放置するのではなく、組織としても積極的に予防の取り組みを進めていく必要があります。正確な実態を把握するためには、データだけでなくアンケート調査なども活用し、多面的での測定が求められます。健康情報の提供やラインケアの強化を通して、従業員の健康をサポートし、アブセンティーイズムの予防につとめましょう。