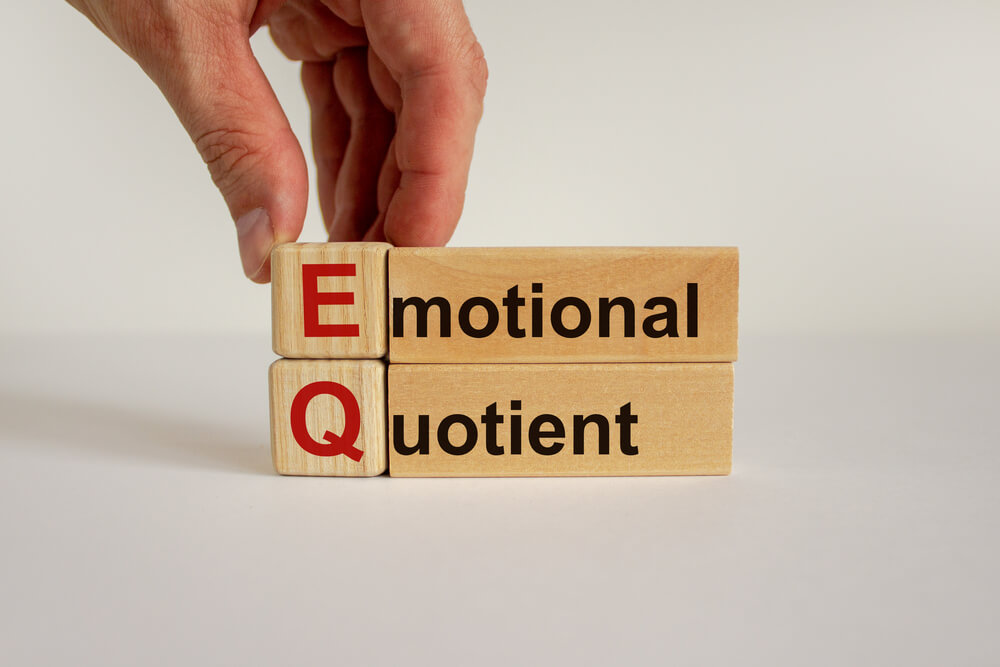日々さまざまな人と関わりながら仕事を進めていくうえで、円滑なコミュニケーションは不可欠なものです。しかし、「周囲に気を使ってなかなか自分の意見を言えない」「違う意見を出されるとついムッとして言い返してしまう」などといった経験がある方もいるのではないでしょうか。アサーションとは、相手を尊重しながらも、自分の気持ちや考えを適切な表現で率直に伝えることです。アサーションを活用すれば、業務を上手く進められるだけでなく、良好な人間関係の構築にもつながり、ビジネスにさまざまなメリットをもたらします。今回は、アサーションの意味やメリット、身につける方法などについて詳しく解説します。

目次
近年注目されているアサーションとは?

はじめに、アサーションの意味や歴史、職場における役割についてチェックしていきましょう。
アサーションとは?
アサーションとは、「自分も相手も大切にしながら、率直・誠実に自分の意見や気持ちを伝える」コミュニケーションスキルの一つです。「断言」「断定」「主張」などの意味を持つ英語の「assertion」に由来する言葉で、アサーションは「自己主張」「自己表現」と呼ばれることもあります。 自分の意見を伝える方法ではありますが、一方的に主張を押し通して相手を黙らせてしまうのではなく、「お互いの考えや価値観を尊重しつつ、適切な言葉でコミュニケーションを取る」ことに焦点が置かれています。
アサーションの歴史
アサーションの始まりは、1949年にアメリカの心理学者アンドリュー・ソルターが発表した、行動療法の一つである「条件反射療法」だといわれています。もともとは、自己主張が苦手な人に対するカウンセリング技法として活用されていました。その後の1960年代ごろに起きたアメリカにおける黒人差別の解消を目指す公民権運動をきっかけに、「相手を尊重しながらも、適切に自己主張をする」という現在の意味合いで使われるようになりました。
日本国内にアサーションという考え方が持ち込まれたのは1980年代です。心理学者でアサーションの第一人者とされている平木典子氏がアメリカで学び、トレーニング体系を日本人向けにつくったことで国内にも広まりました。
アサーションの職場での役割
職場においても、アサーションの意味合いや役割はほぼ同じです。ただし、アメリカでの公民権運動のように、社会問題に対する意見主張という大きな枠組みではなく、従業員同士や取引先、顧客などとの日常的なコミュニケーションをより円滑に行うためのスキルとして捉えられています。コミュニケーションの得手、不得手や職種、職域にかかわらず、研修などを通して従業員全員が活用できることを目指します。
アサーションが注目される背景

アサーションが注目され広まりをみせているのには、いくつかの背景があります。アサーションを活用すれば、お互いの違いを理解し尊重する力を養え、その場の空気感や相手の表情・しぐさといった細かな変化が見えにくいオンライン上のコミュニケーションの円滑化にも役立つと考えられています。
多様性(ダイバーシティ)の尊重
少子高齢化やグローバル化によって、企業で働く人材はますます多様化していくとみられています。組織の競争力向上を目指すうえでも、多様な人材がそれぞれの強みを活かして働けることが重要ですが、異なる価値観、バックグラウンドを持つ人々が協働し、組織として成果をあげていくためには、相互理解が欠かせません。アサーションは、お互いの考え方を尊重しつつ自らの意見も適切に述べるためのスキルであるため、ダイバーシティを推進するにあたって大きな役割を果たすと考えられています。
ハラスメント防止意識の高まり
「◯◯ハラ」という言葉が増えているように、社会全体がハラスメントに敏感になっている今、ハラスメントを恐れて指導を難しく感じている、コミュニケーションの取り方に悩んでいるという管理職も多いかもしれません。ハラスメントと捉えられることなく適切に指導する、伝えるための方法として、アサーションスキルに注目が集まっています。
メンタルヘルス対策の推進
アサーションは、組織のメンタルヘルス対策の一環としても有効な取り組みです。アサーションの考え方が職場に広まり、自分の意見を率直に伝えられるようになったり、良好なコミュニケーションが行われたりすることで、メンタルヘルス不調に陥る要因の一つである職場の人間関係にも良い影響を与えると考えられます。誰もが安心して自分の意見を発言できる「心理的安全性」の高い職場の実現にも寄与するでしょう。
非対面コミュニケーションの増加
コロナ禍を経てテレワークが浸透し、非対面コミュニケーションの機会が増加したことも、アサーションが注目される理由の一つといえます。チャットやメールを用いたやり取りでは、表情や話しぶりによる細かなニュアンスが伝わらないため、意図しない形で相手が受け取ってしまうこともあるでしょう。対面でのコミュニケーションの頻度が少ない中でも、的確に意思疎通を行い、業務を円滑に進めていくためにも、アサーションは有効と考えられます。
企業がアサーションを取り入れるメリット

アサーションを取り入れると、職場のコミュニケーションが活性化するだけではなく、従業員のメンタル不調の予防などにもつながります。ここでは従業員がアサーションを身につけることによって得られるメリットを紹介します。
職場の人間関係が良好になる
アサーションを取り入れて従業員が上手な自己表現を身につければ、立場や価値観の違いを超えて円満な関係を築けるようになります。相手を尊重しつつ対等な立場で議論ができるため、社内のコミュニケーションが活性化されるでしょう。
厚生労働省が実施した「令和5年雇用動向調査結果」によると、令和5年中の転職入職者が前職を辞めた理由について、男女ともに上位に「職場の人間関係が好ましくなかった」が挙げられており、職場の人間関係の良し悪しは働きやすさに大きく関与していることが示唆されます。アサーションを取り入れ、日常的に行われる職場でのコミュニケーションの質が向上すれば、健全で良好な人間関係の構築が期待できます。
意見が言いやすくなる/交渉力がつく
議論やコミュニケーションにおいては、言葉の選び方一つで誤解や摩擦、深刻な対立が生まれてしまうことも少なくありません。アサーションを身につけると、相手を不快な気持ちにさせることなく、より率直に意見を言いやすくなることが期待できます。ハラスメントの発生予防にもつながり、「風通しの良い職場」作りの第一歩となるでしょう。また、ビジネスにおけるさまざまな「交渉」シーンでも役立ちます。
さらに、チームや部署のメンバーとの相互理解が深まり、意欲的に仕事に取り組もうとする雰囲気や働きやすい環境が醸成されれば、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。
業務が円滑に進む
従業員同士で適切な意見交換が行えるようになると、業務の効率化、ひいては組織全体の生産性向上につながるでしょう。何らかのトラブルや問題が発生した時も、相手を否定することなく、懸念点を的確に伝えられるため、衝突や摩擦を防ぐことができます。また、情報のすれ違いなど、業務の停滞につながるようなコミュニケーションの課題が生じにくくなるため、スムーズに業務が進むことが期待できます。
従業員のストレスが軽減される
アサーションによって従業員同士が適切な意思疎通を行えるようになると、働くうえでのストレス軽減が見込めます。例えば忙しくて周りに協力を求めたい時などに、その要望を適切に伝えられる環境があると、自分だけが我慢している、不満を溜め込んでいるような状況が発生しにくくなります。人間関係のストレスなどが引き金となるメンタル不調の予防にもつながるでしょう。
アサーションにおける4つの自己表現タイプ

アサーションでは、コミュニケーションスキルを以下の4つに分類しています。自分や相手の自己表現タイプがどれに当たるかをチェックしてみましょう。
アグレッシブ:攻撃的タイプ
アグレッシブとは相手の気持ちを無視して、自分の意見や価値観を押し付けるタイプです。自分の意見が正しいと思い込んでいて、相手を言いくるめて優位に立とうとします。意見をはっきりと言えるのは良いのですが、周囲との軋轢が生じやすく、結果的に組織に損害を与える事態になりかねません。
ノンアサーティブ:非主張的タイプ
ノンアサーティブとは、自己主張が苦手で、自分よりも相手の主張を優先するタイプです。優しくて控えめな人が陥りやすく、根底に「相手に嫌われたくない」「否定されたくない」という思いがあります。
ノンアサーティブタイプの人は、自分の意見を抑えこんでいるためストレスを抱え込みがちです。また相手の意見に従っているので、責任感が薄かったり、言い訳が多くなったりする傾向もあります。
パッシブアグレッシブ:非主張的かつ攻撃的タイプ
パッシブアグレッシブは、表面上は相手の意見を受け入れつつも、内面では攻撃的な意思を持っているタイプです。やる気をなくして不貞腐れたような態度を取ったり、本人のいないところで愚痴をこぼしたりと、相手に直接言葉を投げかけること以外の方法で相手をコントロールしようとします。
アサーティブ:バランスタイプ
アサーティブとは、アグレッシブとノンアサーティブの良いところをバランス良く兼ね備えているタイプです。相手の気持ちに配慮したうえで、自分の意見を伝えられます。また場の空気を読み、状況に応じて適切な言葉や態度で表現できます。アサーティブタイプの人は良好な人間関係を構築できるので、ストレスも溜め込みにくいでしょう。4タイプの中では、アサーティブタイプが目指すべき理想の姿といえます。
アサーションのトレーニング方法

アサーションを身につけるには、自分の自己表現タイプを注視しながら、いくつかのコミュニケーションスキルを意識して相手と接していくのが効果的です。ここでは、アサーションのトレーニング方法を紹介します。
【考え方】アサーション権の理解
まずはアサーション権について理解することが必要です。アサーション権とは、「人として誰でも認められていること、してもよいことの権利」です。アサーションを理解していても、「頼まれたら断りにくい」「なんとなく相手に申し訳なくて頼みづらい」と考える人もいるかもしれません。しかし、アサーション権に照らすと、人は「罪悪感を持たずに断ってもよい権利」も「引け目を感じず頼みごとをしてよい権利」も持ち合わせています。「誰もが主張してもよい」ことを理解したうえで、自分の意思に沿わない結果になったとしても腹を立てることなく、互いを尊重し、時に歩み寄りながらコミュニケーションを重ねることが大切です。
【考え方】ABCDE理論のフレームワーク
ABCDE理論は、アメリカの臨床心理学者・アルバート・エリスが提唱した思考法「ACB理論」を拡張した思考法です。Activating events(出来事)、Belief(信念、認知)、Consequences(結果)に、Disputation(論証)、Effect(影響)を加えたもので、ネガティブな捉え方をポジティブな思考・感情に転換していくフレームワークです。
出来事(A)そのものが、結果(C)につながるのではなく、出来事(A)に対するネガティブな捉え方(B)に反する論拠(D)を見つけることによって、新しい思考のパターン(E)を生み出し、ポジティブな結果(C)に変えるという考え方をします。このフレームワークを用いて、柔軟な思考を身につけることが、建設的なコミュニケーションを図るアサーションの定着につながります。
アドバンテッジリスクマネメントでは、対人コミュニケーションの基礎能力とされるEQ(感情マネジメント力)向上を目的とした研修を提供しています。アサーションはEQを構成するうちの一つ(対人関係知性)に分類され、アサーション能力の向上にも役立ちます。
【コミュニケーション】DESC法を活用する
DESC(デスク)法とは、以下の4つの順番に主張を伝えるコミュニケーション手法です。
| ①describe(描写する) | 主観を交えず、客観的に状況を伝える |
| ②explain(表現する) | 主観的に自分の意見や気持ちを表現する |
| ③suggest(提案する) | 相手にも寄り添った打開策や解決策を提案する |
| ④Choose(選択する) | 相手の意見を受け、自分の行動を選択する |
これらは、相手を尊重しながら、わかりやすく自分の意見を伝えるのに役立ちます。また、人事担当者や上司が他の従業員や部下に接する際には、これに加えて今後についてのフォローや相談しやすい空気感を心がけるなど、次につながる言動や雰囲気を意識しましょう。
【コミュニケーション】Iメッセージを意識する
次に、I(アイ)メッセージで伝えましょう。I(アイ)メッセージとは、主語を「わたし」にして意見を伝えるコミュニケーション手法のことです。相手に要望や異なる意見を伝える際、「あなた(YOU)」を主語にすると、相手を否定しているように受け取られる可能性があります。例えば、「あなたはこの業務をやっておいて」といった表現は、命令的に聞こえることもあるでしょう。一方で、「わたし(I)」を主語にして、「この仕事をやってもらえると助かります」と伝えると、相手に配慮した柔らかい印象となり、自分の気持ちも伝わりやすくなります。
【コミュニケーション】非言語コミュニケーションも心がける
言葉で伝える以外にも、表情や声・態度・ボディランゲージなどの非言語コミュニケーションにも気を配る必要があります。適切な言葉を使っていても、表情が硬い、口調が強いような場合、攻撃的な印象を与えることがあるため、相手も気持ちよく対応できる接し方を心がけましょう。
詳しいトレーニング方法は以下の記事でも紹介しています。
企業におけるアサーションの活用例

アサーションは日々の業務はもちろん、人事評価や面談、採用面接などの場面でも活用できます。従業員や応募者と対等なコミュニケーションが取れ、適切な人材育成、人材の確保につながります。
面談や面接では、評価する側の上司が威圧的な態度になりやすく、従業員や応募者は率直な意見を言いにくいものですが、アサーションを身につけることで、お互いを尊重して冷静かつ気持ちの良い会話ができ、その後の業務やコミュニケーションもスムーズに行えるでしょう。
従業員のアサーションを高めるポイント

職場内にアサーションを浸透させるには、定期的な社内研修と継続的な実践を行っていく必要があります。従業員へ行う重要な研修のひとつとして取り組むのがおすすめです。
アサーションへの理解を深め、研修を実施する
職場にアサーションを浸透させるには、ハラスメント研修会などと同様に全社員を対象とした社内研修に組み込むのがおすすめです。研修には、「アサーションとは何か」「アサーションの必要性」「自己表現タイプのチェック」「実践方法」などを取り入れると良いでしょう。実施には社内で講師を立てる、外部から講師を呼ぶ、オンラインセミナーを受講するなどさまざまな方法があります。
また、アサーションの意味を理解したうえで、ロールプレイングを行えるとより効果的です。ロールプレイングでは参加者同士でいくつかの事例をもとに、アサーションを意識した会話の練習をすれば、自分の自己表現タイプを自覚するきっかけにもなります。実演が難しい場合は、座学研修のワークに組み込むのも良いでしょう。
厚生労働省「こころの耳」では、アサーションを学ぶグループワークやロールプレイングを含んだマニュアルを無料で配布していますので、併せてチェックしてみましょう。
■労働者個人向けストレス対策(セルフケア)のマニュアル実践編
現場で実践しフィードバック/フォローする
さらに研修で学んだことを現場で活かせているか確認し、不十分な場合にはフォローやフィードバックを行いましょう。
会議や日頃の会話の中で意識できているか、相手だけではなく自分も含めてチェックを行います。定期的に研修会を行うなど振り返る機会を作りながら継続的にトレーニングを実施し、周囲とともに意識していくことが大切です。
アサーションを実践し、コミュニケーションを活性化させよう

アサーションは職場のコミュニケーションを円滑にし、従業員の心身の健康を保つのに役立つコミュニケーションスキルです。相手の意見を尊重しつつ、率直に自分の意見も表明できる環境は、心理的安全性が高く、従業員にとって働きやすいといえます。円滑なコミュニケーションが取れると、問題解決や議論の質が高まり、組織全体の生産性向上も期待できるでしょう。アサーションを企業全体に浸透させ、従業員一人ひとりが活躍できる職場環境の構築を目指しましょう。