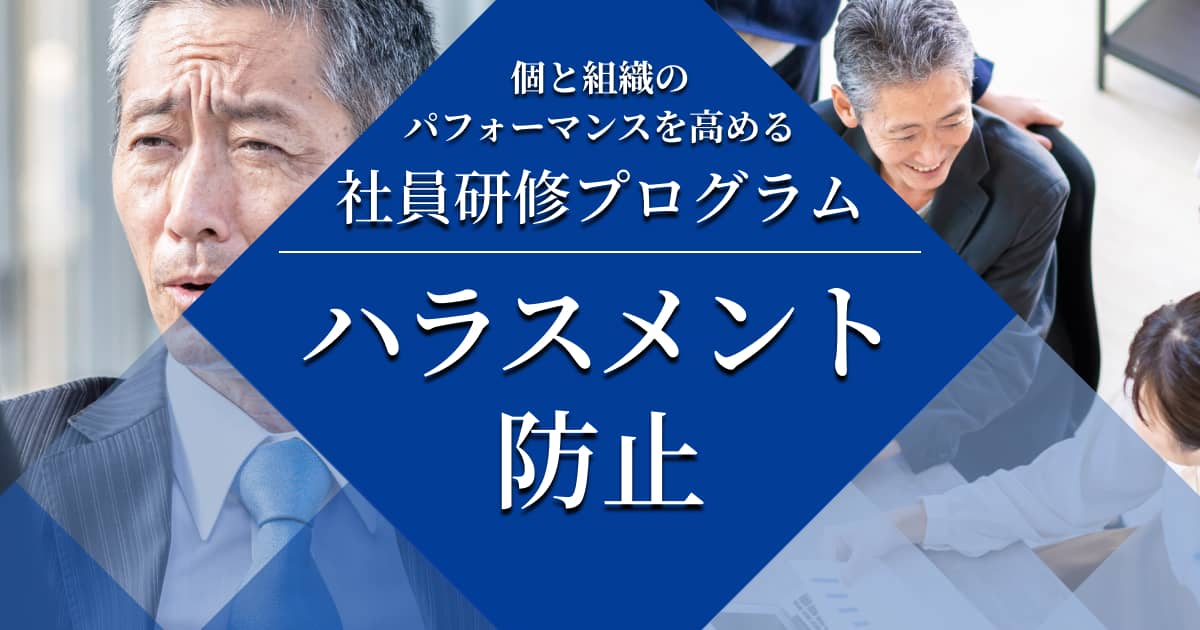ハラスメント相談窓口は「形だけ」でなく、実効性のある運用が不可欠です。本記事では、ハラスメントによる心身への影響や、組織の生産性低下を防ぐため、相談窓口の重要な役割を解説。社内・社外の設置方法や、従業員が安心して利用できる仕組みを事例を交え詳しくご紹介します。信頼される窓口設置を目指しましょう。
「アドバンテッジ カウンセリング」は、従業員の悩みやハラスメントの相談を受ける窓口としても活用いただけるカウンセリングサービスです。ハラスメントの早期対応と再発防止を図り、健全で風通しのよい職場づくりをサポートします。
目次
ハラスメント相談窓口とは?

ハラスメント相談窓口とは、職場で起こり得るさまざまなハラスメントや、ハラスメントの可能性がある問題について相談を受けつけ、解決に向けた支援を行うものです。「明らかなハラスメント行為」だけを対象とするのではなく、「グレーゾーン」とされる行為や、ハラスメントの兆しがある段階での声を受け止めることも、ハラスメント相談窓口の役割の一つです。形式的に「窓口を設置した」だけでは不十分で、実際に相談が寄せられたときに、実効的な対応ができる体制を整えておくことが求められます。
ハラスメント相談窓口が必要な理由

ハラスメント相談窓口の設置は、法的義務を果たすこと以外にも重要な役割があります。次に、相談窓口を設置する必要性についてご紹介します。
法的義務への対応
2020年6月の労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)の施行・改正(中小企業は2022年4月~)、および男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、すべての事業者は職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント(マタニティ/パタニティハラスメント)を防止するため、適切な措置を講じることが義務づけられています。企業は、ハラスメント防止に向けた方針の明確化や、発生後の迅速かつ適切な対応など、さまざまな措置をとらなければなりません。
そのうち、「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」への対応として、相談窓口の設置および従業員への周知が求められています。法令違反に対する直接的な刑事罰はないものの、厚生労働大臣による指導や勧告の対象となる場合があります。これらに従わなければ企業名が公表される可能性もあるでしょう。
ハラスメント問題の早期解決・再発防止
ハラスメント問題の早期解決を図るうえでも、相談窓口の存在は不可欠です。いわゆるグレーゾーンの言動やハラスメント発生の兆候が見られる段階で相談を受けられれば、事態が深刻になる前に対処することも可能です。
また、相談窓口を通じて寄せられる声の中には、特定のハラスメント行為に関する相談だけでなく、職場の人間関係や組織風土に関するものも含まれます。組織の中で表面化していない問題を把握することで、よりよい組織へと改善していくためのヒントが得られるでしょう。
【関連コンテンツ】
アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)とは?職場での事例と対策方法をご紹介
【パワハラ対策の前に】パワハラが発生するメカニズムとは?背景にある行為者と職場の要因を解説
安心して働ける職場づくりの実現
ハラスメント相談窓口は、従業員が安心して働ける職場をつくるうえで重要な役割があります。つらい気持ちや不安を吐露できる場があること、相談を通して解決の糸口が見えてくることで、ハラスメント被害者の心理的な負担を軽減できます。
窓口の設置などを通してハラスメント防止の姿勢をきちんと示すことは、従業員が働くうえでの安心感につながり、ひいては定着率や生産性にも好影響を与えるでしょう。
ハラスメント相談窓口の種類と特徴

ハラスメント相談窓口は、社内の担当者が対応するケースと、外部サービスに対応を委託するケースの2種類に大別されます。続いては、社内/社外それぞれの相談窓口の特徴をご紹介します。
社内の相談窓口
社内の相談窓口は、企業の体制によって異なるものの、一般的に人事労務部門やコンプライアンス部門の管理職や従業員の中から選ばれた相談員や、産業医、カウンセラーなどが対応します。担当者が職場の事情を詳しく知っているため、状況を把握しやすく、スピーディーな対応が期待できることが特徴です。
一方で、相談の事実がハラスメントの行為者(加害者)や周囲に知られてしまうのではないか、相談したことで不利益を受けてしまうかもと考え、相談を控えてしまう懸念もあります。また、担当者がハラスメント対応に関する十分な知識を持っておらず適切な対応ができない、行為者が社内で強い影響力を持つ人物の場合、経営上の損失や担当者自身の不利益を恐れて公正的な判断、厳しい処分ができないケースもあるでしょう。
社外の相談窓口
社外相談窓口は、メンタルヘルスやハラスメントに強い外部カウンセリングサービスや弁護士などに委託する仕組みです。第三者機関のため客観的な判断が期待でき、委託先によっては企業に事実を伏せたうえで相談可能な点が強みといえます。社内に専門知識を持つ人材が不足している企業や、独自体制が難しい小規模な企業に特に有効です。自社のニーズに合った委託先を選ぶことが重要となります。
社外の無料相談窓口
国や都道府県が設置する無料の相談窓口もあります。ただし、これらの窓口は「従業員向け」のもので、企業がこれらの利用を促す、あるいは従業員が実際に利用した場合でも、企業が負う「ハラスメント相談窓口の設置義務」を果たしたものとは認められないため注意しましょう。
職場で起こるハラスメント事例

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たす行為を指します。
1.優越的な関係性に基づくもの: 職務上の地位や人間関係など、相手が抵抗しにくい関係性を背景に行われる言動。
2.業務上の適正な範囲を超えたもの: 業務上、明らかに必要性がない、または社会通念上不適切な言動。
3.就業環境を害するもの: 労働者が身体的・精神的に苦痛を感じ、能力の発揮に悪影響を及ぼすこと。
ただし、客観的な視点から見て、業務上必要かつ適切な指示や指導は、パワーハラスメントには含まれません。
社会問題として大きく取り上げられることの多い代表的なハラスメントだけでなく、新たに「〇〇ハラ」と名付けられ、認知が広がっているハラスメントも存在します。職場で発生しやすいハラスメントについて押さえておきましょう。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメントとは、職務上優位な立場を利用して業務の適正な範囲を超えた言動を行い、就業環境を害する行為です。
例:上司から部下への暴言や過剰な叱責
新任の上司や異動者など、情報や人間関係で不利な立場にある人へのいじめ
【関連コンテンツ】
パワハラを相談されたらどうする? NG対応&人事がとるべき流れを解説
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメントとは、性的な言動によって労働条件を不当に悪化させたり、職場環境を不快にしたりする行為です。男性から女性へだけでなく、同性間、女性から男性へのセクハラも存在します。
例:身体への不必要な接触
性的な冗談や話題の強要 など
【関連コンテンツ】
セクハラを相談されたらどうする? NG対応&人事がとるべき流れを解説
マタニティハラスメント(マタハラ)/パタニティハラスメント(パタハラ)
マタハラ/パタハラとは、妊娠中、出産前後の女性やそのパートナー、育児を行う従業員への嫌がらせです。法改正によって男性の育休取得は進みつつありますが、制度の利用を阻む風土が残っているのも現状です。
例:妊娠を報告した女性従業員に否定的な反応をする
育休取得を申し出た男性従業員にキャリア上の不利益を示唆する
上記以外にも、職場では以下のようなハラスメントが問題視されています。
- モラルハラスメント(モラハラ)
- 時短ハラスメント(ジタハラ)
- エイジハラスメント(エイハラ)
- ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
- カスタマーハラスメント(カスハラ)
実際にあった職場のハラスメント事例について、詳しくは以下の記事で紹介しています。
【関連コンテンツ】
職場であったハラスメント事例7選|代表的なハラスメントや企業の責任を解説
ハラスメントの種類は多すぎる?ハラスメント別の定義と一覧紹介。職場における対策方法も解説
ハラスメント相談窓口の企業事例

実際にハラスメント相談窓口の設置・運用を行っている企業の事例をご紹介します。
【相談窓口と現場の対話で安心感を醸成】食品販売業D社
食品販売業のD社は、ハラスメント防止と職場環境改善に注力しています。防止方針や具体例、相談先を記載した冊子とイントラネットで周知を徹底。産業カウンセラー資格者による電話・メールの相談窓口を常設しています。さらに、年1回の個人面談や無記名アンケートで職場の問題を早期に把握。相談と現場把握を組み合わせ、従業員が安心して働ける仕組みを構築しています。
参考:あかるい職場応援団【第34回】「コミュニケーションの活性化で働きやすい職場作り」
【内容に応じた多様な相談窓口の設置】株式会社アドウェイズ
株式会社アドウェイズは、ハラスメント防止のため、「通報」と「相談」の2経路で計6種類の窓口を用意しています。匿名利用が可能な「目安箱」や外部カウンセラーへの相談など、多様な選択肢を設けることで、相談へのハードルを下げています。これにより、ハラスメントの潜在リスク把握やメンタルヘルス相談も可能に。窓口情報はポータルやチャットで定期的に周知し、利用しやすい体制を整えています。
参考:東京都産業労働局TOKYO ノーハラ企業支援ナビ
【相談のハードルを下げるハイブリッド活用】株式会社加藤研磨製作所
株式会社加藤研磨製作所は、ハラスメント対策に注力しています。相談しやすいよう、営業部長や工場長など複数の社内窓口担当者を設置。小規模ゆえの懸念に対応するため、外部の「ハラスメントダイヤル」にも直接相談できるようにしました。また、パンフレット配布や就業規則への記載を通じて、継続的な啓発と、会社全体での防止の姿勢を浸透させています。
参考:東京都産業労働局TOKYO ノーハラ企業支援ナビ
ハラスメントの相談を受けたときの対応方法

ハラスメント防止に向けた取り組みの大前提は、「ハラスメントを生み出さない」ための意識改革と職場風土の醸成です。しかし、万が一の事態に備え、ハラスメントが発生した場合の対応を知っておくことも重要です。最後に、ハラスメントの相談を受けた際の対応方法についてご紹介します。
1.被害者からの相談対応
ハラスメント相談窓口の担当者は、勇気を出した相談者に寄り添いながら、丁寧にヒアリングを行う必要があります。相談の秘密は守られ、不利益な扱いを受けないことを明確に伝えなければなりません。聞き取りでは、フラットに聞くことを心がけ、主観的な判断や否定、追及は避けます。事実確認まで加害側を一方的に責めるような発言は控えましょう。励ますつもりの言葉もかえって逆効果になるため、慎重な対応を心がけます。相談者にメンタル不調の兆候が見られる場合は、医療機関の受診勧奨や行為者との接触回避など、迅速な措置が必要です。
窓口担当者が留意したいセカンドハラスメントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連コンテンツ】
セカンドハラスメントとは?種類や原因、対策について解説
パワハラを相談されたらどうする? NG対応&人事がとるべき流れを解説
2.ハラスメント事実の確認
相談を受けた後は、ハラスメント行為の事実確認を行います。客観的な証拠(メールや録音など)の有無を確認し、必要に応じて第三者へのヒアリングや、相談者の同意を得た上で行為者本人へ聞き取りをします。ただし、相談者に内密にしたい意向があればその限りではありません。
特に、被害者と行為者の意見が食い違う場合には、第三者からの意見聴取が重要です。調査中は、被害者が行為者と接触しないよう配慮しましょう。
3.ハラスメント認定の判断、処分の検討
収集した情報をもとに、ハラスメントがあったかどうかを総合的に判断します。難しい事案では、弁護士などの外部有識者を交えた調査委員会を設置することも検討しましょう。ハラスメント行為者への処分は、被害の深刻度を考慮するほか、就業規則や過去の判例を参考にしつつ、謝罪・配置転換・戒告・減給・降格など段階的に検討します。
4.被害者のフォロー・行為者への説明
被害者には、安心して働き続けられるよう継続的なサポートを行います。行為者へは、処分で終わりにせず、「なぜハラスメントに該当するか、何が問題だったか」の理解を促し、再発防止のために研修やカウンセリングを行うのが望ましいです。
ハラスメントが認められなかった際は、被害者が納得できず法的措置に発展するケースがあるため、弁護士などの専門家と事前に連携しておくと安心です。
5.再発防止に向けた対策の検討・実施
ハラスメント事案への対応が終了したら、再発防止に向けて職場環境全体の見直しを図りましょう。ハラスメントの背景要因にコミュニケーション不足や組織風土の問題がある場合は、研修の実施や制度の見直しを行います。
ハラスメント防止の取り組みは、一度の研修や改善で終わりではなく、継続的に実施していきます。また、定期的に振り返りを行い、問題がないかどうかの再点検が大切です。
【関連コンテンツ】
ハラスメント行為者の行動変容を促すためには?再発防止に向けて企業がすべきこと(前編)
ハラスメント行為者の行動変容を促すためには?再発防止に向けて企業がすべきこと(後編)
相談窓口を整備し安心して働ける職場へ

職場のハラスメント対策では、「発生させない」ことはもちろん、「万が一の際に声を上げられる環境づくり」が不可欠です。相談窓口は、法的義務として設置するだけでなく、実効的な仕組みで運用することで、問題の早期解決と従業員が安心して働ける環境を整備できます。窓口は社内担当者による内製、または外部の専門サービスへの委託があり、役割を考慮し検討しましょう。