健康診断の結果、「所見あり」と判定された従業員には「就業判定」を実施します。就業判定は産業医と連携して行うものですが、定められた期間内に実施する必要があるため、スピーディーな対応が不可欠です。本記事では、就業判定の目的や実施の流れ、判定を踏まえてとるべき措置などについて詳しく解説します。
目次
就業判定とは
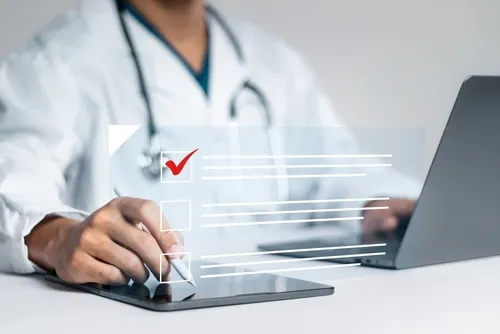
就業判定とは、健康診断の有所見者に関して、業務を継続して問題ないか、あるいは何らかの業務制限の必要があるか否かを判断することです。事業者である企業は、就業上の措置の必要性について医師(産業医)から意見を聴取しなければなりません。医師の意見を踏まえ、職場や業務内容の変更、労働時間の短縮など、適切な措置をとる必要があります。
就業判定の目的

就業判定の目的は、就業の制限や、業務負担の軽減によって働きやすい環境を提供し、従業員の健康を守ることです。また事業者は、労働契約法(第5条)や労働安全衛生法(第3条の1)において、労働者の心身の安全と健康を確保する義務を負っています。就業判定は、これらの法的義務を果たす意味でも重要なプロセスです。
健康診断から就業判定までの流れ
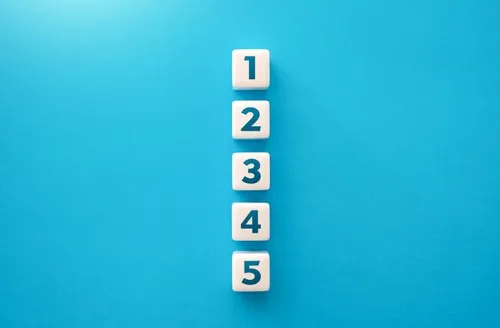
健康診断から就業判定までの流れを整理しておきましょう。
①健康診断の実施
事業者は、雇用形態を問わず一定要件を満たすすべての従業員に対し、年1回医師による定期健康診断を行う義務があります。従業員が健診機関へ出向くか、バス健診など巡回健診を依頼する方法でも実施可能です。実施時期は繁忙期を避け、十分な案内期間を設けることが受診率向上につながります。
➁健康診断結果の受領
健康診断後は、事業者が医療機関から個人別の結果表を一括で受領し、異常所見の有無を確認して有所見者を把握します。常時50人以上の従業員を雇用する企業は、定期健康診断結果報告書を作成し労働基準監督署へ提出する義務があります。結果は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当するため、5年間の保管期間中も情報漏えいや改ざんを防ぐ適切な管理が不可欠です。
③従業員への結果通知
事業者は、異常の有無にかかわらず健康診断結果を遅滞なく従業員へ通知し、正確な健康情報を提供する義務を負います。結果は要配慮個人情報のため、渡し間違いや漏えい防止に配慮しつつ、迅速に個人へ手渡します。有所見者には産業医や保健師による保健指導を行うよう努め、従業員が自ら健康管理に取り組める環境づくりが必要です。
④【異常所見がみられた場合】産業医による意見聴取および就業判定
健康診断で異常所見があった従業員には、就業上の措置について産業医の意見を聴取する義務があり、その期限は健診実施日から3ヵ月以内です。意見聴取にあたっては、従業員の作業環境や労働時間、深夜作業の回数や時間、作業負荷状況、過去の診断結果などを情報として提供します。
続いて、産業医が健康診断の結果をもとに、働き続けられるか、特別な対応が必要かを判断します。就業判定の分類は、「通常業務」「就業制限」「要休業」の3つです。
就業判定の実施にあたって職場の管理・体制面でお困りごとはございませんか?アドバンテッジリスクマネジメントでは「就業判定スポットサービス」として就業判定に範囲を狭めた産業医サービスをご用意しています。就業判定にお困りの際はぜひお気軽にご相談ください。
⑤就業上の措置の決定
健康診断で異常所見があった場合、事業者は産業医の就業判定や医師の意見を参考に、従業員本人の意見も聞いたうえで就業上の措置を決定します。措置内容は、労働時間の短縮や業務変更など健康への配慮が中心ですが、収入面の影響もあるため、十分な説明と理解が不可欠です。必要に応じて産業医が同席し、円滑な話し合いを行うこともあります。
健康診断の判定区分
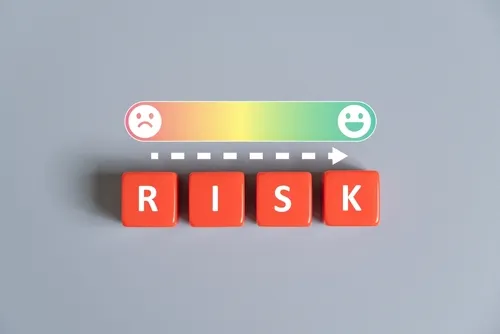
判定区分とは、健康診断を実施した医療機関の医師が、検査結果や数値をもとに判定する区分のことです。判定基準や診断区分と表記されることもあります。主にA~Eの5段階で評価されますが、各段階の定義は医療機関によって異なります。なお、判定には産業医はかかわりません。
| A判定 | 異常なし | 今回の健康診断では異常が認められず、健康状態に問題がない |
| B判定 | 軽度異常 | 検査結果に軽度の異常が認められるが、病気の可能性は低い |
| C判定 | 要経過観察 | 病気へと進行する可能性があるため、生活習慣の改善と経過観察を必要とする |
| D判定 | 要再検査または要精密検査 | 病気の可能性が高いため、再検査・精密検査を受ける必要がある |
| E判定 | 要治療・治療中 | 速やかに治療を受ける必要がある/既に治療を受けている場合は治療を継続する |
健康診断の判定区分と就業判定の違い
健康診断の「判定区分」と「就業判定」は、どちらも健康診断結果に基づく判断ですが、判断する担当者や目的が異なります。判定区分は、健康診断を行った医療機関側が、検査数値や問診結果から異常の有無や精密検査の必要性を分類するものです。これはあくまで医療的な診断区分であり、健診医が担当します。
一方、就業判定は、産業医が判定区分や職場環境の情報を踏まえて、従業員が通常通り勤務できるか、業務制限が必要か、あるいは休業が望ましいかを判断するものです。つまり、判定区分は「健康状態の診断」、就業判定は「働き方に関する判断」という違いがあります。
健康診断の判定区分で就業判定は可能?

健康診断の判定区分は、従業員の健康状態の把握という点では重要な情報ですが、それだけをもとに就業判定を行うことは適切とはいえません。判定区分はあくまでも医学的に健康リスクを評価したものであり、「働ける状態かどうか」を直接評価する指標ではありません。
また、判定区分自体も実施機関によって基準値が異なるため、同じ数値でB判定とされることもあれば、C判定とされる場合もあります。健康診断の判定区分に加え、従業員の実際の労働環境や産業医の意見などを総合的に考慮し、就業判定を行うことが求められます。
就業判定の区分と具体的な措置内容

就業判定は、通常業務・就業制限・要休業の3つの区分に分かれています。それぞれどのような対応が求められるのかチェックしておきましょう。
| 通常業務 | 制限なし |
| 就業制限 | 勤務の制限が必要 |
| 要休業 | 休暇・休業の措置が必要 |
通常業務
「通常業務」の場合は、通常の業務に従事させて問題ありません。就業上の措置として何らかの制限を加える必要もありません。
就業制限
「就業制限」は、従業員の負担を軽減するため、勤務に制限を加えることが必要です。どのような制限を行うかは、従業員の個々の状態・状況に応じて検討します。産業医は、現在の仕事を継続することで健康状態の悪化や疾病の発症につながるリスクがないかなどを、医学的観点から判断します。就業制限を実施し、従業員に改善・回復の傾向がみられたら、医師の判断のうえで通常業務に戻せます。
【就業上の措置の例】
- 勤務地の変更
- 業務内容の転換
- 労働時間の短縮
- 深夜勤務の回数の制限
- 出張回数の制限
- 作業環境の改善 など
要休業
「要休業」は、従業員を療養させるため、一定期間勤務させないことが求められます。休暇や休職の措置が必要です。
就業判定の注意点

就業判定を実施する際の注意点をご紹介します。
従業員本人の理解と同意を得る
健康診断の結果を理由に、またその従業員の健康を確保するために必要な範囲を超えて、不利益な取り扱いは禁止されています。就業上の措置の内容によっては、収入が減少するなどのデメリットが生じる可能性があるため、対象となる従業員と十分な話し合い、理解を得てから実施しましょう。従業員のプライバシーに配慮したうえで、その従業員が所属する職場/部署の管理監督者にも、目的などについて丁寧に説明を行い、その必要性を理解してもらうことが重要です。
専門家と連携し、スピーディーに対応する
就業判定を適切なプロセスで実施できなかった場合、従業員の健康が損なわれてしまうおそれもあります。法令遵守という点でも、速やかな対応が求められます。しかし、産業医との面談日程の調整や進捗管理、健康診断結果の記録管理など、健康診断実施後の業務は膨大かつ煩雑です。担当者の負担を減らしつつ、効率的でスピーディーな対応を実現できる健康診断業務の外部委託も検討しましょう。
健康診断業務と産業医・産業保健師との連携について、詳しくはこちらのお役立ち資料『健康診断業務ガイドブック』をご覧ください。
健康診断実施後に事業者に義務付けられている措置

最後に、就業判定の流れのおさらいも兼ねて、健康診断の実施後に事業者がとるべき対応を、関連する法律とともに解説します。法律により定められた措置を適切に実施する義務があるため、確実に対応しましょう。
健康診断結果の通知・産業医からの意見聴取
健康診断の結果は、速やかに従業員に通知しなければなりません。(労働安全衛生法第66条の3、労働安全衛生規則第51条の4)また、異常な所見がみられた従業員については、事業者は産業医から就業判定に関する意見を聴取しなければなりません。(労働安全衛生法66条の4)意見聴取は、原則として健康診断を実施した日から3ヵ月以内に行う必要があります。
また、事業者は必要に応じて当該従業員の情報(労働時間、作業環境、深夜勤務の回数や時間、過去の健康診断結果など)を産業医に提供する義務があります。(労働安全衛生規則51条の2)
【チェックポイント】
☑健診結果を従業員に通知しましたか?
☑健診結果に異常所見があった従業員への措置について、医師などから意見を聞きましたか?
就業上の措置の決定
産業医からの意見を踏まえ、事業者として就業上の措置が必要と判断した場合は、適切な措置をとらなければなりません。(労働安全衛生法66条の5)従業員の健康状態や就業環境を考慮し、具体的な内容を決定します。就業判定の内容および産業医からの意見は、健康診断の個人票に記録します。また、必要に応じて、産業からの意見を衛生委員会に報告し、対策を検討しましょう。
【チェックポイント】
☑医師などからの意見聴取を参考に、業務内容の変更や労働時間の短縮など、適切な対応をとりましたか?
健康診断結果の記録・保管
事業者には、健康診断の結果を記録しておく義務を負います。(労働安全衛生法第66条の3)結果については「健康診断個人票」を作成し、5年間保存しておかなければなりません。(労働安全衛生規則第51条)
【チェックポイント】
☑健康診断個人業を作成し、各健康診断で定められている期間、健診結果を保存していますか?
労働基準監督署への報告
常時50人以上の従業員を雇用している事業者は、定期健康診断の実施後速やかに、所轄の労働基準監督署へ定期健康診断結果報告書を提出する必要があります。(労働安全衛生規則52条)報告書には産業医の記名(署名)が必須です。なお、2025年1月1日より電子申請が義務付けられています。
【チェックポイント】
☑定期健康診断の結果を、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に提出しましたか?
【努力義務】保健指導・受診勧奨
事業者は、健康診断の結果、特に健康保持に努める必要性があると判断された従業員に対して、医師や保健師による保健指導を受けさせるよう努めなければなりません。(労働安全衛生法第66条の7)産業医がいる事業場では、産業医が所見の確認を行い、保健指導の実施や再検査・治療のための受診勧奨を行うことが多いです。
【チェックポイント】
☑特に健康保持の必要がある従業員に対して、保健指導を実施していますか?
適切な対応で従業員の健康を守りましょう

就業判定は、法律において事業者に実施が義務付けられているものです。従業員の健康を守るとともに、企業が安全配慮義務を果たすうえでも重要な役割があります。産業医と綿密に連携し、就業制限や休業の必要が生じた場合には、従業員本人ともよく話し合って措置を決めましょう。






