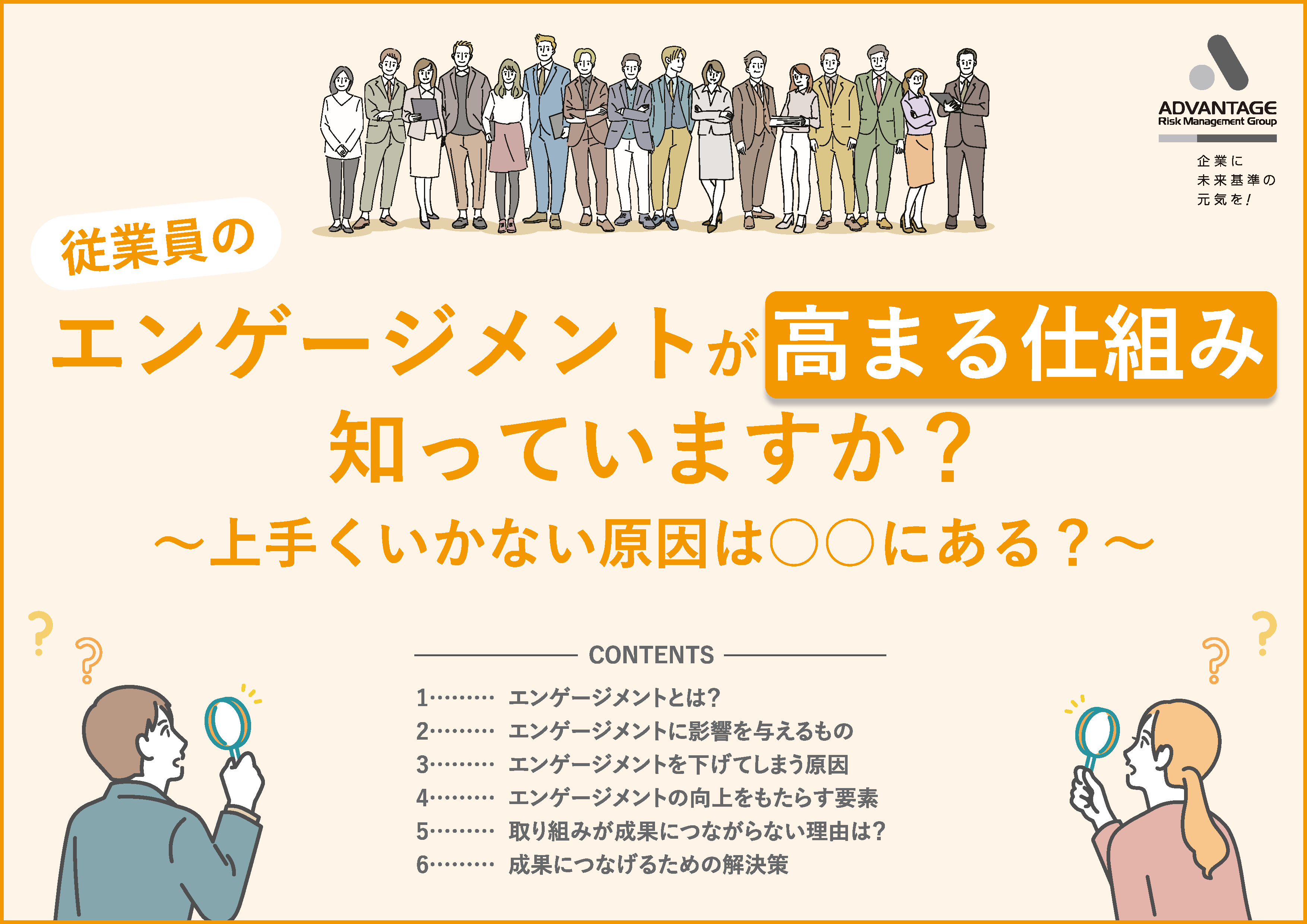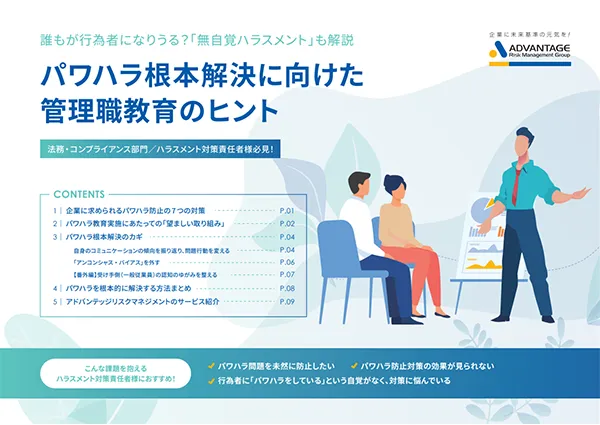人手不足が深刻になる中では、1人の退職が組織全体に大きな影響を与えることにもなりかねません。働き方の価値観が変化し、転職をポジティブなものとして捉える見方も浸透しつつある今、企業は従業員の離職防止により注力していくことが求められます。今回は、従業員の離職原因や離職防止に有効な施策をご紹介します。
目次
離職防止とは

離職防止とは、従業員が企業を辞めることを未然に防ぐために行う対策です。離職防止の例として「働きやすい職場環境の整備」「従業員との定期的な1on1の実施」「社内コミュニケーションの促進」などといった取り組みが挙げられます。従業員が退職する背景には、いくつかの理由が関係しています。そのため、離職の防止には1つの手段に偏らず、さまざまな角度からのアプローチが必要です。
企業が離職防止施策を行う理由とメリット

まずは、企業が離職防止施策に取り組むべき理由とそのメリットについて解説します。
人材の流出防止
少子高齢化による生産年齢人口の減少は、人手不足に直結する深刻な問題です。人材の確保そのものが難しくなる中では、貴重な人材をいかにして定着させるかが特に重要です。長く働く従業員が社内にいることは、ノウハウや知識の蓄積という点でも強みとなります。生産性の向上や事業の安定的な継続につながり、組織全体が高い競争力を維持できます。
エンゲージメント向上
離職防止の取り組みは、従業員のエンゲージメント向上を後押しします。企業への信頼や愛着が育まれ、「この職場で働き続けたい」という気持ちが強くなれば、仕事そのものに対する意欲も高まります。前向きに働く従業員の存在は、周囲にもよい影響をもたらし、チームワークの強化や自律的な組織への成長につながるでしょう。
〇目次:エンゲージメントとは?/エンゲージメントに影響を与えるもの/エンゲージメントを下げてしまう要因/エンゲージメントの向上をもたらす要素/成果につなげるための解決策 他
〇仕様:9ページ
採用・教育コストの削減
一定数の離職はあらかじめ見込まれているものの、離職者が多いと新たな採用や教育にかかるコストが膨らみます。特に、近年は売り手市場で採用競争が激化しており、採用単価も上昇しています。新卒や若手の早期離職が続いた場合は、コストが回収できず大きな損失につながりかねません。従業員の離職を防止できれば、これらのコストを削減でき、限られたリソースを本来注力すべき事業に集中させられます。
企業のイメージアップ
人材が定着している企業は、外部からも「働きやすい職場」として好印象を持たれやすくなります。求人媒体によっては、離職率を明示しなければならないケースもあり、求職者にとっても「長く働ける環境かどうか」は、応募する上で重要な基準の1つです。従業員の満足度が高いことは、顧客や取引先などからの信頼にもつながり、企業全体の価値向上が期待できます。
従業員が離職する原因

次に、従業員が離職する主な原因についてチェックしていきましょう。
職場の人間関係が良くない
離職の原因となりやすいのが、職場の人間関係の悪さです。厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、男性の9.1%、女性の13.0%が前職を辞めた理由に「職場の人間関係が好ましくなかった」ことを挙げました。「その他の理由」を除くと、女性では最多、男性でも2番目に多い結果となりました。
職場での心理的安全性が低く、基本的なコミュニケーションが取れない、相談や提案がしづらいなど、安心して仕事ができる土壌そのものがなければ、意欲的に働くことは難しいです。従業員の定着には人間関係以外の要因も深く関連していますが、協力的な関係性が築けない職場では、業務そのものが魅力的であっても、働き続けたいとは感じにくいでしょう。また、ハラスメントなどの問題が放置されている場合も、職場の雰囲気が悪化し離職につながります。
参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
待遇や労働環境に不満がある
給与や勤務時間、業務量の多さなど、待遇や労働環境への不満も離職理由として非常に多いです。例えば、給与が低い、残業や休日出勤が多い、上司が残業をしていると帰りにくい雰囲気があるなどが挙げられます。
また、昇進したのに給与がほとんど変わらない、成果を出しているのに評価されないなど、「頑張りが認められない」と感じている場合、モチベーションが下がり離職してしまいます。なかには、過重労働によって心身に不調をきたし、退職を余儀なくされるケースもあるでしょう。
希望する働き方が実現できない
働き方に対する価値観が多様化し、自分の希望するワークライフバランスが実現できないことを理由に離職を選ぶ人もいます。プライベートの時間を大切にしたいという人だけでなく、特に育児や介護、病気の治療などといったライフイベントと仕事との両立が必要な従業員は、柔軟な働き方を認められない場合、「働き続けるのは難しい」と感じてしまいます。
自分自身の成長が実感できない
「このまま働き続けても成長できない」と感じることも、離職の引き金となります。特に、高い成長意欲や向上心を持つ従業員にとって、スキルアップやキャリア形成の見込みが薄い環境は、モチベーションの維持が難しいです。ルール重視で工夫を認めない、現状維持を好むなど、チャレンジしづらい職場に不満を募らせて離れていってしまいます。
組織の将来に不安がある
事業の成長が見込めない、ビジョンが曖昧であるなど、キャリアの見通しが立てにくいと、離職に至ることがあります。企業の将来性に信頼が持てなければ、従業員は自分の未来を託せません。安心して生活が送れるよう、より安定した環境を求めて離職を決断してしまうのです。
離職が近い可能性のある従業員の特徴

離職しそうな従業員には、いくつかのサインが見られます。ここでは、周囲が注視しておきたい3つの特徴をご紹介します。
新しい仕事を引き受けない
離職を考え始めた従業員は、新しい業務やプロジェクトへの参加を避けるなどの傾向が見られるようになります。責任感のある人ほど「最後までやり遂げられないものは引き受けたくない」と、消極的な態度をとることもあるでしょう。
会議での発言が減る、集中力が下がったように見えるなどの変化は、企業や仕事に対して関心を失っている表れかもしれません。ただし、メンタルヘルス不調を抱えている場合にも同様の変化が表れるケースがあるため要注意です。
コミュニケーションが少なくなる
挨拶や雑談が減った、ランチなどでの交流を避けるようになったなど、コミュニケーションが少なくなることも、離職を決意した人に見られるものです。水面下で転職活動を進めている場合、離職の意思を悟られないよう意図的にコミュニケーションを減らしている可能性もあります。
勤務時間や休暇の取り方が変化する
遅刻や早退が多くなる、残業を控える、直前の申請による休暇の取得が増えるような場合、転職活動が本格化しているサインかもしれません。残業に協力的だった人が急に定時で帰るようになるなど、「もうすぐ辞めるから自分には関係ない」という心の変化が働き方に表れていることもあるでしょう。
ただし、遅刻や早退は心身の不調によるものであったり、残業の減少や休暇の取得には、プライベートの事情が関わっていたりするケースもあるため、日ごろからコミュニケーションをとり、その背景を慎重に把握する必要があります。
離職が近い従業員の特徴については、上記の他、こちらの記事でも具体的に紹介しています。
離職防止に有効な施策12選

続いては、離職防止に効果的な12の施策をご紹介します。ぜひ、自社の取り組みを検討する際のヒントとしてください。
ビジョンやパーパスを発信・浸透させる
ビジョンやパーパスは、企業の進むべき道を示す指針であり、従業員にとって行動の基盤となるものです。従業員の中で、「なぜこの企業で働くのか」「企業の方向性に共感できるか」が揺らぐと、エンゲージメントが低下し、離職につながるおそれがあります。
ビジョンやパーパスを浸透させるには、経営者などトップが自らの言葉で、継続して発信していくことが大切です。すべての従業員に伝えられるよう、社内会議や社内報、コミュニケーションツールなどを活用しましょう。自分の仕事がパーパスの実現と結びついているという実感が、やりがいや貢献意識の向上を促し、定着に寄与します。
業務を見直し負担を軽減する
長時間労働など、強い負担がかかった状態が続くと、従業員の心身の疲労やモチベーションの低下を招き、離職に至る場合が懸念されます。業務の棚卸しやITツールなどの導入で効率化を図る、各従業員の業務分担を見直すなど、従業員の負担を軽減しましょう。
評価制度や報酬体系を見直す
納得感のある評価制度と適切な報酬体系を整えることも、離職防止に有効です。定量・定性の両面から評価できる仕組みや、個々のスキルや成果に応じたプラスアルファの報酬が得られる制度などを、明確な基準とともに定めましょう。自らの頑張りや成長が目に見える形で評価されることで、エンゲージメントの向上も期待できます。
従業員の成長・キャリア形成を支援する
成長を実感できる環境かどうかは、従業員が組織にとどまるかを左右する要因の1つです。研修やスキルアップの支援、社内公募制度の整備などを通して、一人ひとりが描くキャリア像の実現、挑戦へのサポートが求められます。個々のキャリア観に寄り添うことが、長期的な定着につながります。
ワークライフバランスを整える
リモートワーク、コアタイム制度の導入、有給休暇の取得促進など、仕事とプライベートどちらも大切にできる働き方を整備すると離職防止に役立ちます。また、副業や兼業を許可することは、企業にとって離職の回避が期待できる他、従業員のスキルアップやモチベーション向上といった副次的な効果も得られます。従業員の声をもとに制度設計を行い、必要に応じて見直していきましょう。
社内イベントでコミュニケーション活性を図る
社内イベントは、従業員のエンゲージメントを高め、組織への愛着心を育てます。離職防止の他、従業員同士のコミュニケーション活性化をもたらします。例えば、懇親会やチームビルディングを目的とした企画、スポーツイベントなど、取り組みはさまざまです。業務とは異なるリラックスした雰囲気の中では自然と会話が生まれやすく、共通の趣味や関心を見つけるきっかけにもなるでしょう。職場のコミュニケーション活性化の方法については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
1on1やメンター制度を導入する
定期的な1on1ミーティングを通じて、従業員の現状や目標、仕事への姿勢をしっかりと把握し、相互理解を深めましょう。また、従業員が安心して相談できる人が近くにいるかどうかは、離職を防ぐ上で重要なポイントです。1on1ミーティングやメンター制度の導入は、従業員の仕事の悩みや不安の解消、孤立の防止だけでなく、上司や先輩との信頼関係を深めていく点でも大きな役割を果たします。
従業員のコミュニケーション力を高める
離職の原因になりやすい職場の人間関係においては、ストレスの原因にならないような、円滑なコミュニケーションが取れることがカギとなります。研修を実施してコミュニケーションの方法を学ぶのも1つの方法です。アドバンテッジリスクマネジメントでは、対人コミュニケーションの基礎能力とされるEQ(感情マネジメント力)向上を目的とした研修を提供しています。
管理職のマネジメントスキルを高める
職場の人間関係を起因とする離職の中には、「上司との関係性」が関与していることも多いです。適切なマネジメントは、職場全体の雰囲気を良好にし、従業員の意欲や定着率の向上に寄与します。上司によるハラスメントや不適切な言動を防ぎ、指導や育成のスキルを高められるような研修を実施しましょう。
○目次:企業に求められるパワハラ防止の7つの対策/パワハラ教育実施にあたっての「望ましい取り組み」/パワハラ根本解決のカギ①~②/【番外編】一般従業員への教育 他
○仕様:12ページ
従業員のメンタルタフネス度を高める
メンタルタフネス度とは、困難な状況に直面しても感情に左右されず、解決に向けて行動できる力のことです。つまり、ストレスに対処するためのスキルを意味します。
この力は生まれつきの性格ではなく、トレーニングによって身につけられる能力です。ストレスとの向き合い方を学ぶことで、問題が発生したときにも冷静に対応できるようになり、仕事に対する熱意や組織への帰属意識が高まりやすくなります。結果として、エンゲージメントの維持・向上にもつながります。
○目次:メンタルタフネスとは/メンタルタフネス度を高めるメリット/メンタルタフネス度を高める方法/組織でメンタルタフネス度を測るべき理由 他
○仕様:16ページ
悩みを相談できる窓口を整備する
職場の人間関係やキャリアの迷い、メンタルヘルス不調など、従業員のさまざまな不安や悩みを相談できる窓口を設けます。「話を聞いてもらえる場所がある」という安心感を与えるとともに、第三者という異なる視点からの意見を聞くことで、「まだこの職場でやれることがあるかもしれない」と気持ちを転換できる場合もあります。カウンセリングや相談窓口は誰でも気軽に利用できること、相談の秘密は守られることなどを周知し、積極的な利用を促しましょう。
従業員アンケートやサーベイを実施する
従業員の「仕事に対する姿勢」や「チーム内で起きている見えにくい課題」を把握するには、アンケートやサーベイ、ヒアリングの実施が有効です。定量的・定性的なデータを収集して現状を明らかにすることで、組織内の問題をいち早く察知し、的確な改善につなげられます。サーベイは一度実施して終わりではなく、定期的に繰り返して変化を読み取り、その時々の課題に応じた柔軟なアプローチを行いましょう。
企業の離職防止における成功事例

最後に、従業員の離職防止施策の成功例を、実際の企業の取り組みからご紹介します。
株式会社アジャイルウェア
ソフトウェア開発を行う株式会社アジャイルウェアは、本当の「働きやすい」を追求するため、多角的な取り組みを実施しています。
【取り組み例】
- 実際のオフィス・バーチャルオフィスの両環境を整備
- フルフレックス制の導入(創業時より・理由の申告や上司の承認不要)
- スキルアップ支援制度
- 副業の許可
- 隔週週休3日制をトライアル実施(2022年より)
【成果】
- 残業時間をエンジニア職で月10時間、全体で月20時間程度に抑制
- 年次有給休暇取得率83.2%を達成
- 従業員アンケートで95%がウェルビーイング向上を実感
- 中期的な離職率の低下
- 求人の応募数増加
社会福祉法人南風会
福祉関連事業を手がける社会福祉法人南風会は、「働きやすさと働きがい」という方針のもと、離職防止に向けた施策を行っています。
【取り組み例】
- 役員と職員の定期面談、意見箱設置による職場改善の意見収集
- 介護業務の棚卸し・見える化
- 残業を前提としない業務計画の策定
- 職種ごとの業務定義と時間給設定による人事評価の標準化
- ICT利活用推進
- 計画的な年次有給休暇の取得促進
【成果】
- 離職率が2004年の6割超から2021・2022年度は約10%まで低下
- 残業時間は1人あたり年間約11時間に抑制
- 年次有給休暇取得率64.7%を達成
- 休暇取得の風土が醸成され、取得意向も向上
株式会社USEN-NEXTHOLDINGS
株式会社USEN-NEXTHOLDINGSは、経営統合に伴い働き方改革に着手しました。管理するマネジメントから脱却し、自律的に働ける環境づくりに取り組んでいます。
【取り組み例】
- コアタイムなしのスーパーフレックスタイム制度の導入(非稼働日の設定、週休3日も可能)
- 全従業員を対象としたリモートワーク制度の導入
- リモートワーカーの認定制度の導入
- 業務・時間・コスト削減案の募集と実施
【成果】
- 従業員の自律性・効率性が向上し、残業時間が減少
- 業務スピード向上、管理コスト削減
- リモートワークを組み合わせ、育児とフルタイム勤務の両立が実現
- マネジメント層の意識改革促進
株式会社ZOZO
ファッション通販事業などを展開する株式会社ZOZOは、従来より独自性のある働き方を推進してきましたが、業務の多様化などから、より部門に適した働き方を検討し、実現しています。
【取り組み例】
- 変形労働時間制の導入(1日8時間勤務×週休2日または1日10時間×週休3日)
- 業務属人化の解消、会議時間の調整、引継ぎの円滑化などの業務改善
【成果】
- 残業時間が約63%減少し、業務効率が改善
- 年休取得率は低下せず、休みやすい環境醸成が実現
- 休日が増えたことで心の余裕が生まれ、仕事の精度・モチベーション向上
従業員一人ひとりに向き合い、信頼関係を築く

職場の人間関係や労働環境、キャリアの不安、ワークライフバランスなど、従業員が離職に至る背景は人によって異なります。企業として制度設計の見直しなどを柔軟に進めると同時に、サーベイや1on1を通して従業員の変化を早めに察知し、丁寧にコミュニケーションを取り、必要なサポートを行うことが大切です。一人ひとりと真摯な姿勢で向き合うことが、従業員からの信頼獲得につながり、定着率を高めるでしょう。